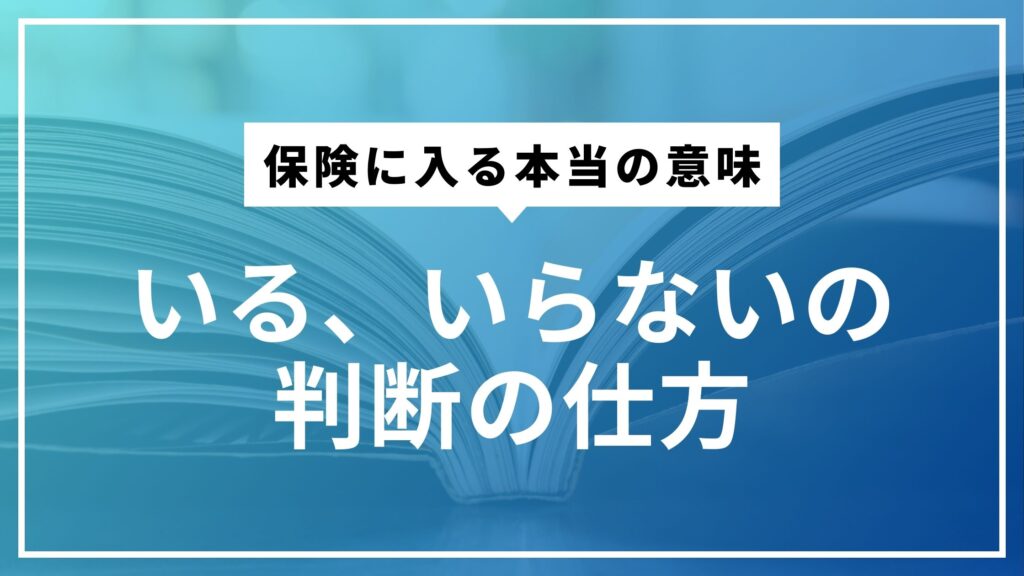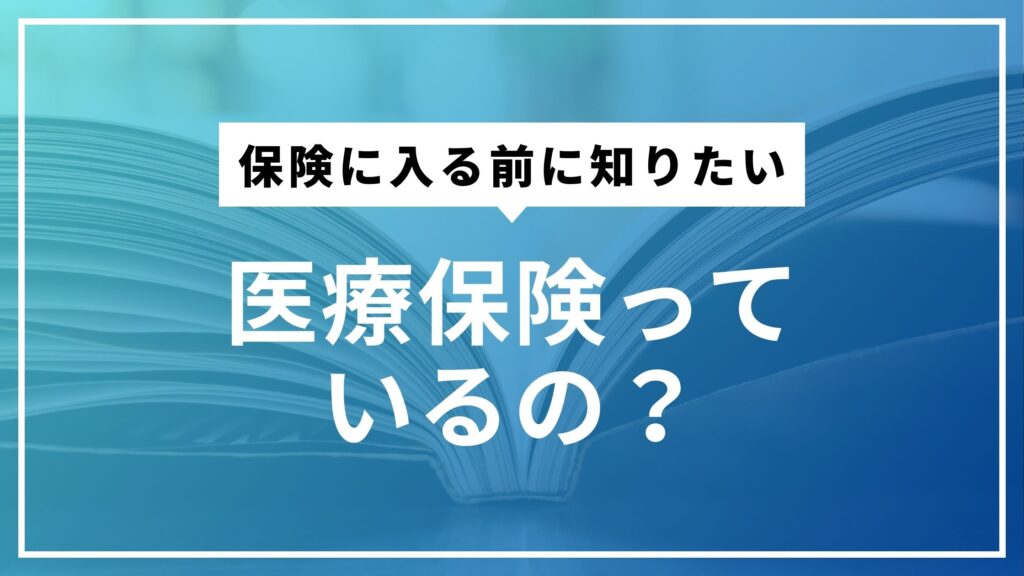保険屋さんのタケモリです。
今回は、火災保険の損しないかけ方というテーマでお話させていただきます。
そもそもですが、家ってなかなか燃えないじゃないですか。
「おお、今日も燃えてるね!」
みたいになったことがある人は、基本的にいないと思います。
それにも関わらず、ほとんどの家は火災保険をかけています。
燃える可能性は低いのに、なんで保険をかけるのでしょうか?
それは、万が一のときの損害を自分ではカバーできないからです。
けど、ただ保険をかければいいというわけではありません。
例えば、建物に5,000万円の火災保険をかけていて、実際に全焼したにも関わらず保険金が全額でないケースがあります。
安いからって理由で適当に保険をかけていると、痛い目を見るかもしれません。
そこら辺も踏まえてお伝えしていきますので、よければ最後までご覧ください。
目次
火災保険の補償内容と活用方法
まず基本的なことで、火災保険は建物にかけるものと、家財にかけるものの2種類があります。
家財とは、家具・家電のことで、家から持ち出しができるものは家財だと思ってもらって大丈夫です。
逆に、家から持ち出しができない室外機とか、独立洗面台とかは建物の一部として扱われます。
人によっては、建物の火災保険はかけていて、家財にはかけていなことは珍しくありません。
その場合は、建物に対しての火災保険しか使えないのでご注意ください。
補償の種類
火災保険にはどんな保障があるのかを整理します。
- 火災
- 落雷
- 風災
- 水災
- 飛来/水濡れ
- 不測かつ突発的な事故
メインの保障はこのようになります。
けっこうありますね。
それぞれ詳しく解説します。
火災
誰でも想像がつく通り、家が燃えたら保険金がもらえます。
例えば、建物の火災保険に5,000万円、家財に1,000万円の保険をかけていて全焼したら、合計で6,000万円の保険金がもらえます。
建物の火災保険金の設定の仕方はいくつかありますが、平米数で簡易的に計算されることが多いです。
30平米のワンルームに何億円もの火災保険をかけるなんてことはできませんし、逆に、数万円だけ保険をかけるなんてこともできません。
ただ、家財の保険に関しては、ある程度自由に保険金額を設定できます。
一応、家財の保険をいくらくらいに設定すればいいかという目安を各保険会社で出せはするんですけど、その金額通りに入っている人は少ないです。
家財の目安の出し方はかんたんで、世帯主の年齢と、家族構成を入力するだけです。
例えば、世帯主の年齢40歳、大人2人、子ども1人の場合を計算すると、家財の保険金額の目安は、1,240万円と計算されます。
目安の金額をお客様に伝えると、けっこうな割合で「いや、うちにそんな高価なものはない」と言われます。
別に目安通りに保険をかけないといけないなんて決まりはないので、500万円とか、300万円とか決め打ちで設定してもいいと思います。
なにも保険をかけてないよりマシなので。
それとよく、「なんで年齢と家族構成で計算されるの?」と質問されることがあります。
例えば、20代の一人暮らしと、40代の子どもがいる世帯では、おいている家具・家電の量や質が違ってくるはずです。
僕がひとり暮らしをはじめたときは、新生活応援キャンペーンってことで、掃除機・電子レンジ・炊飯器の3点セットを1万円で購入しました。
でも40代、50代でこんな3点セットは、まあ買わないですよね。
だから世帯主の年齢や家族構成は、ひとつの指標になることがわかると思います。
ちなみに、このときに買った掃除機を、ぼくは今でも使っています。
地震保険と火災保険の関係についても、少し触れておきます。
基本的には、地震保険は単体で入ることができなくて、火災保険とセットで加入することになります。
そのときに、火災保険を5,000万円かけるから、地震保険も5,000万円かけようってことはできません。
地震保険は最大でも、火災保険金額の50%までしか保険金を設定できない決まりがあります。
つまり、5,000万円の火災保険をかけている場合だと、2,500万円までしか地震保険はかけられないということです。
ちなみに、下限は火災保険の30%なので、火災保険金額が5,000万円だと地震保険はいちばん安くて1,500万円です。
要するに、5,000万円の火災保険をかけているときの地震保険は、最大で2,500万円、最小で1,500万円になります。
2,500万円と1,500万円の間であれば、自由に地震保険金額を設定できるというわけですね。
風災
風災は、台風で窓ガラスが割れたときの修理代を保険で払ってもらうとかです。
あとはカーポートが飛んでいったとか、物置が壊れたとかでも請求があります。
台風前にかけこみで火災保険に入りたいって言ってくる人がいますけど、基本的に厳しいです。
極端な話、台風シーズンだけ火災保険に入って、一難去ったら解約することもできてしまいます。
なので引受は慎重にならざるを得ないということですね。
自分が入っている保険で確認しておいたほうがいいのは、取り片付け費用まで保険で出るかです。
例えば、台風で自宅の外壁が破損して庭に散乱したとします。
それを集めて撤去するのにも費用はかかるけど、その片付け費用は保険の対象外です。
なんて言われたら、「なんで?」となりませんか?
残存物取片付け費用保険金というのが、対象になっているかチェックしてみてください。
他には、台風で自分の家のものが飛んでいったときに、賠償責任はあるのか?
という質問を受けることがあります。
このときは原則的には賠償責任はありません。
自然災害に対しては、賠償責任はないんですよね。
ただ、台風がくるとわかっていて明らかに飛んでいきそうなものを放りだしている場合はその限りではありません。
皆さん台風の前はしっかり備えられると思うので、基本的に賠償責任はないと思ってもらって大丈夫です。
落雷
落雷事故では、雷が落ちて損害がでたときに保険が使えます。
雷で家が損壊した場合はもちろん対象なのですが、建物よりも家財がやられるパターンの方が多いです。
雷が落ちてテレビが故障したとか、Wi-Fiが使い物にならなくなったとかですね。
ただこのときに、家財の保険に入っていればよかったねとなるんですが、入っていないこともけっこうあります。
僕としてはやっぱり、少しでもいいので家財にも保険をかけておくのがオススメです。
落雷が原因のときの保険金請求で、保険会社から落雷証明書を出してくれと言われることがありますが、そんなものは必要ありません。
修理か交換の見積りをしてもらった業者から、見積りに一筆「落雷による損害」と書いてもらえば、それだけでいいです。
落雷証明書とかそんな聞いたこともないような書類の提出を求めることで、請求するのをめんどくさくして諦めさせようとする思惑なんかは決してないと思います。
水災
水災の支払条件は、床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水となっています。
だいぶ条件が厳しいですね。
なので、ちょっとした損害ではなく、大規模な災害を想定したときの保障といえます。
マンションの2階以上に住んでいる人は水災の保障はなくてもいいと思います。
そこまで水が上がってくることは稀ですよね。
水災は保険料に与えるインパクトがけっこう大きいので、保障をなくしてしまうか迷うポイントです。
でも水災のリスクが高い地域に住んでいる人は、必須の保障です。
大雨による土砂崩れとかも水災の扱いになるので、注意してください。
自分が住んでいるか地域が水災のリスクが高いかどうかは、ハザードマップで調べることができます。
特に、住宅ローンを払い終わっていない方で、保険料が高くなるからという理由で安易に水災を外している方は、今一度考え直してみてください。
保険に入っているのに、経済的に再起不能になったら本当に意味がないので。
土砂崩れや洪水で家は流されても、住宅ローンは流されないことには注意が必要です。
飛来/水濡れ
飛来というのは車が家に突っ込んできたとか、ボールが投げ込まれて窓ガラスが割れたときの保障です。
車で突っ込まれたときは、お前が突っ込んできたんだから、お前の自動車保険から賠償しろって話なんですけど、等級が下がるからとか、最悪保険入ってないと言われだしたら面倒です。
そんなときは、自分の火災保険で対応したほうがストレスはかからないですかね。
まあでも、基本的にそんなに使うような保障ではないです。
どちらかというと、水濡れは意外と請求があるし、支払いが高額になることも多いです。
「水災と水濡れの違いはなんですか?」
と質問されることがあります。
大まかに言うと、大雨などの自然災害が水災、家の水回りからの損害が水濡れというイメージです。
例えば、洗濯機が壊れて床が水浸しになり、床の張替えが必要になったときは水濡れとして保険金がもらえます。
不測かつ突発的な事故
この保障がいちばん火災保険で請求できる可能性があります。
破損や汚損の損害があれば請求できるもので、例えば、子どもがテレビにおもちゃをぶつけて壊したとか、模様替えしているときに家具を壊したとか、そういった日常的なトラブルに対して使用できます。
そんなちょっとしたものに保険をかける必要はないという人もいれば、つけておきたいという人もいてマチマチです。
ちなみに、イラついて壁を殴って壊したとかは請求できませんからね。
あくまでも、不測かつ突発的に起こった事故が対象になります。
火災保険の落とし穴
火災保険金額の決め方を間違って認識している人はけっこう多いです。
「何年も前に建てた家だから、建物の価値は下がっているし火災保険にかける金額を下げておこう」
そう考える方は多いですが、実は必ずしもそうするべきとは限りません。
たしかに、月日が経つにつれて建物の価値が低くなっているのは間違いありません。
でもこれはあくまでも不動産的な考え方です。
保険では、いま同等規模の建物を建てようとしたときに、いくらくらいかかるかを考えて、火災保険金額を決定します。
昔と比べたら物価も建築資材も高騰しているので、もしかしたら当初の費用では家が建てられない可能性もありますよね?
昔は5,000万円で建てた家でも、もしいま火事が起きて建て直すとなったときに、5,500万円が必要ですってなったら困ります。
500万円はどこから捻出すればいいのってなってしまいます。
だから不動産的な価値ではなくて、いま建て直すとしたらいくらくらいかかるかって観点で火災保険金額を決める必要があります。
知らなかったでは済まないトラブル
単刀直入にいうと、保険金額を安く設定しても問題ないと考えるのは危険です。
保険金額が適正な価額より低すぎると、保険金を満額受け取ることができません。
これを業界用語で比例てん補といいます。
例えば、適正評価額が5,000万円の物件に
「家が全焼したとしても2,500万円もらえれば大丈夫でしょ」
と考えて、2,500万円の保険金をかけていたとします。
この状態で、仮に1,000万円分の損害が発生したときに、1,000万円がもらえるかと思いきやそうではありません。
実際に受け取れる保険金は500万円になってしまいます。
適正な評価額5,000万円に対し、保険金額は2,500万円しか設定していませんでした。
つまり本来の50%の割合で保険をかけていたわけです。
この50%という割合は保険金の支払い時にも影響します。
どういうことかと言うと、
全焼して2,500万円がもらえるかと思いきや、1,250万円しかもらえないとか、
1,000万円の被害が出たから1,000万円もらえると思いきや、500万円しかもらえない。
みたいに、比例てん補がかかることになってしまいます。
他には、火災が起きているにもかかわらず、保険金が支払われないケースがあります。
家が燃えているのに火災保険の対象にならないって意味分かんないですよね。
例えば、地震が原因の火災は地震火災といわれていて、これは地震保険の対象になります。
なので地震保険に入っていないと、家が燃えているにもかかわらず、保険金はもらえないということになってしまいます。
「地震保険はなくても別にいっか!」
という人は後を絶ちませんが、地震火災のリスクも踏まえて検討してみてください。
まとめ
今回は、火災保険には建物の家財の2種類があることや、各種保障はどんなものがあるのかなどをご紹介しました。
実際に見積りをとると、特約とか契約期間とか他にもいろいろ検討することがありますが、まずは大枠を抑えることが重要です。
地震火災や比例てん補の話は、けっこう知らない人が多いので、参考にしていただければ幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!