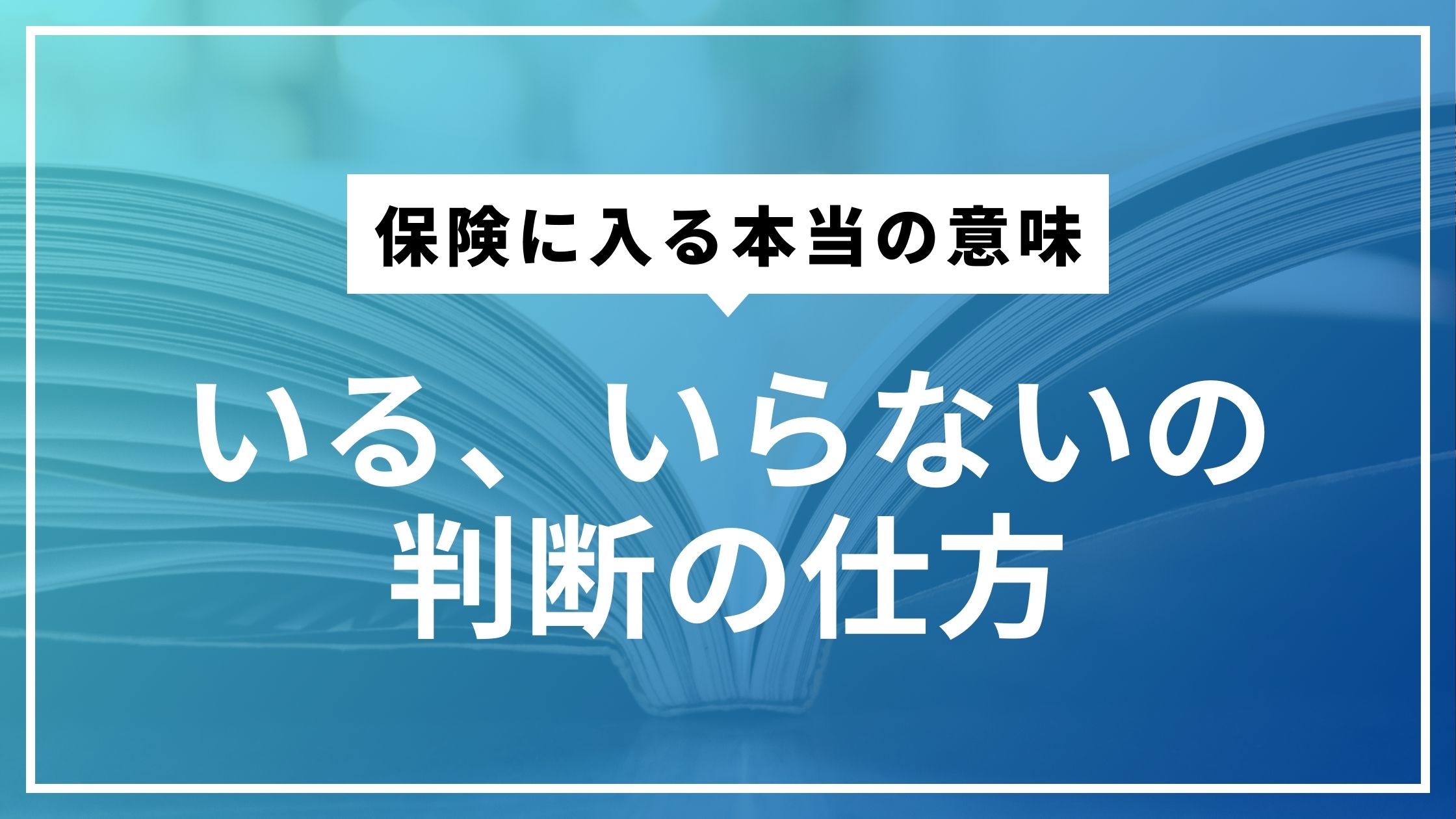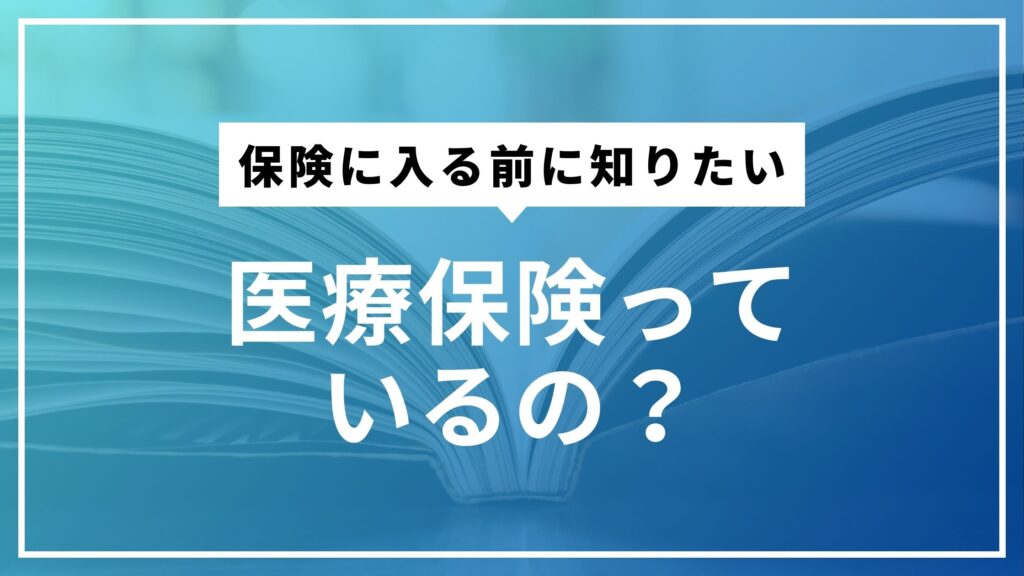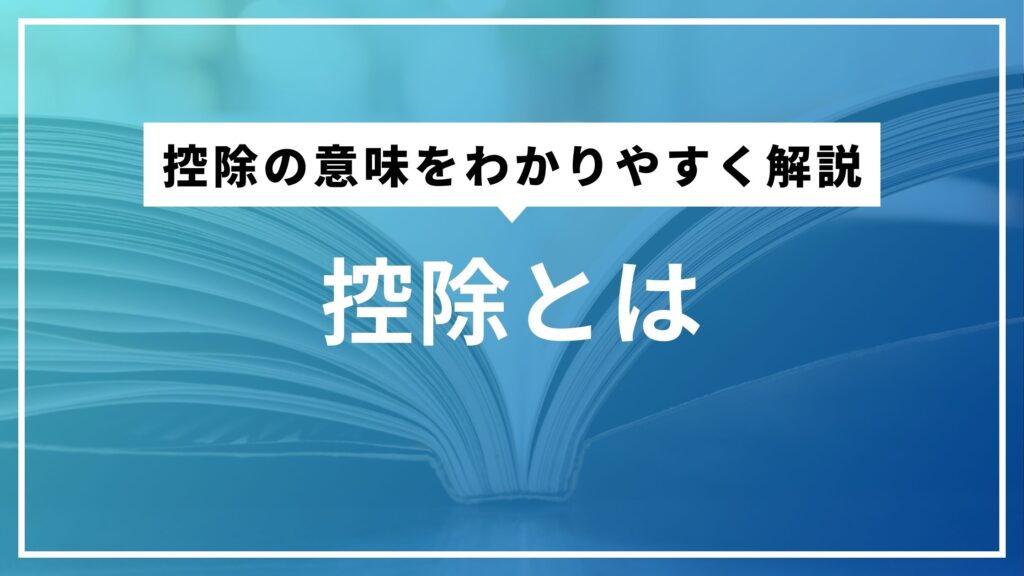こんにちは!
今日はあなたが「知らずのうちに」加入している、とっておきの保険についてお話します。
実は、あなたはすでに最強の保険に入っているんです。
その名を自家保険といいます。
目次
この記事を読む3つのメリット
- 毎月の保険料を最大50%削減できる可能性
- 保険のセールスから身を守れるようになる
- 家計の見直しにも新しい観点が手に入る
保険の見直してめんどくさいですよね。
しかも見直したからって必ずしも内容がよくなるとも限らないし、専門家に相談するのも大変。
そんな方に、そもそも見直すべきかどうかの判断基準になる情報をお届けします。
まずはご自身で保険のいる、いらないを判断してみてください。
毎月の保険料、実は半額で済むかもしれない
保険料の支払いが大変。。というような声をよく聞きます。
日本人の平均月額保険料は約33,000円。
これが高いのか安いのかはよくわかりませんが。
年収2,000万円の人もいれば、300万円の方もいるし、平均値を出されたところでそんなに重要な意味はないのかなと。
それに、掛け捨てか貯蓄性がある保険なのかでも、保険料は全然違いますからね。
で、誰がいくら保険をかけているかはどうでもいいとして、問題なのは必要のない保険に入っている人が多いこと。
「自家保険」という考え方をほとんどの人が知らないと思います。
保険営業職の人でも全然知らないので仕方はありません。
でも自家保険を理解するだけで、
「たしかに保険ってそういうもんだよな」
「この前提から考え直したら、いまの保険いらないじゃん」
ってなる人は少なくないと思います。
「自家保険」ってなに?聞いたことないけど…
簡単に言えば「自分の貯金や収入で対応できるリスクは、わざわざ保険に入る必要がない」という考え方です。
実はこの考え方、アメリカでは当たり前です。
日本人は生命保険が大好きというか、同調圧力に弱いので、みんな保険に入ってたら私も入るって価値観が拭えていません。
例えば、こんな話を聞いたことがあるでしょうか?
世界中のお客さんを乗せた豪華客船が沈没してしまうところです。
乗客の数に比べて、脱出ボートの数は足りません。
なので船長は全員に海に飛び込むように指示を出します。
ですがお客さんはなかなか飛び込もうとしません。
そのときに船長は乗客に対してなんと言って飛び込ませたでしょうか?
- アメリカ人に対して:「飛び込めばヒーローになれますよ」
- ロシア人に対して:「海にウォッカのビンが流れていますよ」
- イタリア人に対して:「海で美女が泳いでいますよ」
- フランス人に対して:「決して海には飛び込まないで下さい」
- イギリス人に対して:「紳士はこういう時に海に飛び込むものです」
- ドイツ人に対して:「規則ですので海に飛び込んでください」
- 中国人に対して:「おいしい食材(魚)が泳いでますよ」
- 日本人に対して:「みなさんはもう飛び込みましたよ!!」
なかなかに皮肉が効いていますが、真実が含まれています。
みんな大学に行くから自分も行く。
やりたい仕事はないが、みんな就職するから自分も就職する。
みんな保険に入ってるから自分も入る。
あ、すみません、これむかしの僕でした。
「飛び込めばヒーローになれますよ」と言われて飛び込める人格になりたいものです。
知って得する!日本の保険の特徴
日本の保険について、知っていますか?
- 世界一の保険大国(一人当たりの生命保険料が世界一)
- 公的保障が世界でもトップクラスに充実
- それにもかかわらず、民間保険の加入率も世界一
つまり、私たち日本人は「保険の掛け過ぎ」になっている可能性が高いんです。
公的保障が充実しているということは、逆説的に社会保険料が高いということですからね。
国からも高額な保険料をとられつつ、民間の保険会社へも無意味な保険料を払うのは避けたいところです。
火災保険から学ぶ、保険の本質
ここで、ちょっと面白い例を見てみましょう。
あなたの家にはおそらく既に火災保険がかかっていますよね?
でも考えてみてください。
- 火災に遭う確率は約0.05%(統計局データ)
- ほとんど人が一生火災を経験しない
ほとんど家なんて燃えないにも関わらず、なぜ多くの方が火災保険をかけているのでしょうか?
答えは簡単です。
火災の被害額が大きすぎて、普通の貯金ではカバーできないから。
これこそが保険の本質なんです。
自家保険から考える、本当に必要な保障とは
では、具体的に考えてみます。
自家保険力のチェック、リスクの分類、必要な保障額の計算の具体例を見ていきましょう。
①自家保険力のチェック(会社員Tさんの例)
現在の貯蓄額:300万円
【内訳】
- 普通預金:100万円(緊急時に備えての貯金)
- 定期預金:200万円
毎月の収入合計:50万円
【内訳】
- 本人給与:手取り30万円
- パートナー給与:手取り20万円
※実家からの支援は考慮しない
つまり収入が50万円、貯金が300万円の夫婦ということになります。
②リスクの分類
保険が不要なリスク例
そもそも貯金やパートナの収入で補填できるものは、保険を掛ける必要がないとお話しました。
保険をかける必要がない状況は、たとえば下記のようなときです。
- 1週間程度の入院
- 軽度の怪我や病気
- 家電の故障
お金がかかったとしても、10万円~30万円くらいではないでしょうか?
貯金や毎月の収入からカバーできる範疇です。
保険が必要なリスク例
- がんなどの重篤な病気
- 住宅の全焼
- 重度障害による長期の収入
数百万円から数千万円の負担が予想されるので、これらはかなり多くの方にとって大打撃ではないでしょうか。
自分の力でカバーするのが難しい。
だから保険をかけるんです。
この前提を忘れてはいけません。
得するか損するかとかはわからないので、保険は保険と割り切ってください。
で、それでもいらないと思う人はいらないってことでいいと思います。
必要な保障額の計算(医療保険)
保険がいるかいらないか整理できて、ご主人の手術・入院に関して保険をかけておいた方がいいと判断したとしましょう。
じゃあ早速、保険の見積りをお願いしよう!
となりがちですが、まだ早いです。
まずは公的保障の整理からしていきましょう。
- 高額療養費制度
- 傷病手当金
まず確認したいのはこの2点ですね。
高額療養費制度は、仮にどんなに医療費が高額になろうとも国が大部分を負担してくれる神制度です。
医療費が一月で100万円かかったとしても、200万円かかったとしても、あなたの手出しは8万円程度になる感じです。
※収入により変動する
もうひとつは傷病手当金。
あなたが会社員であれば使える制度です。自営業の方は対象外となっています。
傷病手当金は、ケガや病気で会社を休んだときに、給与の2/3を補償(最長1年6か月)してくれるありがたい制度です。
民間の保険を検討する前に、高額療養費制度と傷病手当金については知っておいた方がいいでしょう。
で、保険のセールスパーソンはこう言ってきます。
入院したときのベッド代や食費は自己負担しなければなりません。
働けなくなったときの収入の補填としても医療保険は必要です!
まあたしかに間違ったことは言っていません。
でも食費は入院してようがしてまいがかかりますし、はたらけなくなったときってどこまで想定して言ってるの?と思います。
1年くらいの入院を想定してるなら、会社員の方であれば傷病手当金から給料の2/3が補填されます。
じゃあ残りの1/3を医療保険でまかなえばいいねってなるかもしれません。
ベッド代といってもピンキリです。
大部屋に泊まればタダですし、一人部屋だと個室代で数万円かかります。
どこの病院に入院するかで、個室代が2万円になるかもしれませんし、5万円になるかもしれません。
じゃあ医療保険の必要補償額をどうやって計算するの?
仮に手術・入院したとき、一月に20万円かかる想定だっとします。
20万円 ÷ 30日間 = 6,666円
となるので、医療保険の主契約を入院日額7,000円とすると、わりと根拠を持って保険に入ることができるかなと思います。
安全側に見すぎる落とし穴
こんなケースに心当たりのある方は要注意です。
- 会社の保障と個人でかけている保険の重複
- 必要以上の入院給付金
例えば、死亡退職金というものがあります。
死亡したときに会社から500万円支給されるとしたら、必要保障額から500万円を控除してOKですよね。
思わぬところで補償が重複している可能性はあります。
高額療養費制度のことも知らずに高額な入院給付金をつけている医療保険も黄色信号でしょう。
公的補償を踏まえた上で最適な補償額を出したいところです。
死亡保障についてもさらった触れる
- ローン完済後も変わらない保障額
- 子どもの独立後も継続する教育保障
何の根拠もなしに死亡保険金を設定していませんか?
一般的に、長く生きれば生きるほど必要な死亡保障額は減っていきます。
なぜなら、将来に必要となる教育費や生活費などはすべて減っていくからです。
目的を明確にせず、ずっと一定額の保険金をかけ続けるのは無駄がある可能性が高いです。
まとめ:明日からできる保険の見直し
自家保険についてお伝えしました。
パートナーの収入、貯蓄額を既に保険として考えるというものです。
そのうえで保険をかけたほうがいいときってどんなときだろう?と考えるのが第1ステップです。
高額療養費制度や傷病手当金など、日本の社会保障は充実していることも覚えておいてください。
それでも、実際の見直しはちょっと不安…という方は保険の無料相談を検討するのもいいかもしれません。
自家保険や公的保障を考慮して、プロがあなたのアドバイザーとなってくれます。
保険は「備え」であって「投資」ではありません。
プロの考え方を知ることで、本当に必要な保障が見えてくるはずです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!