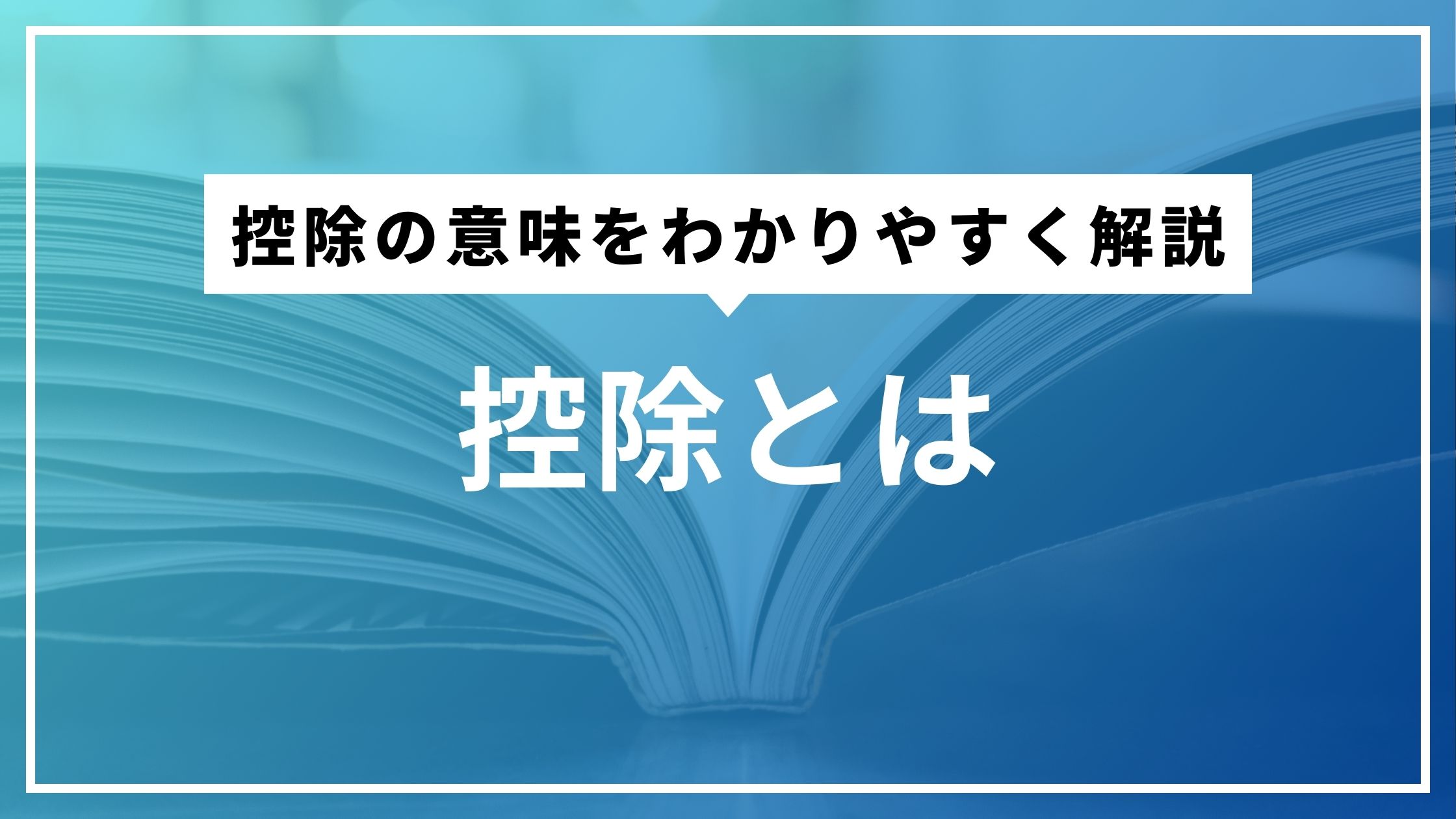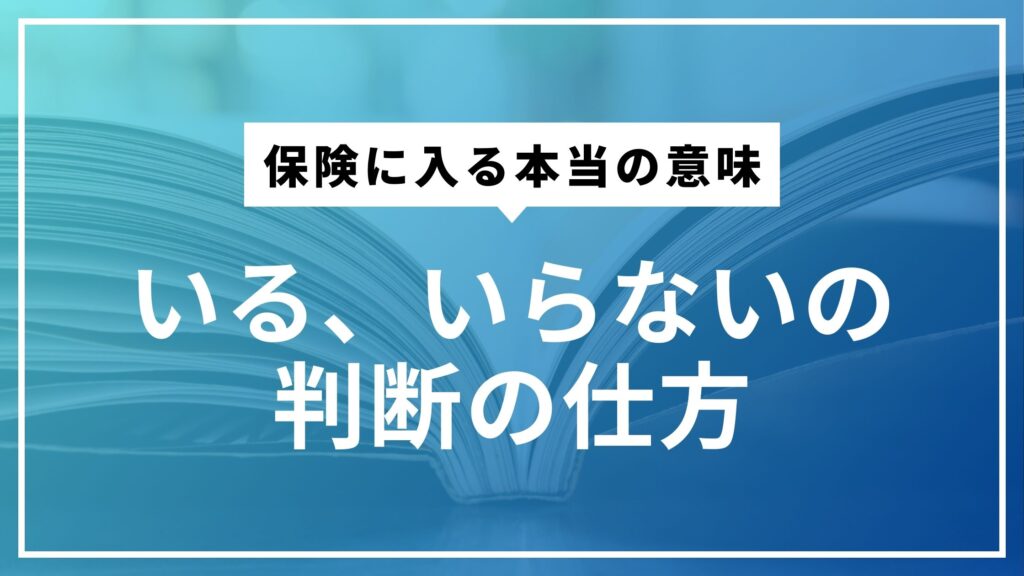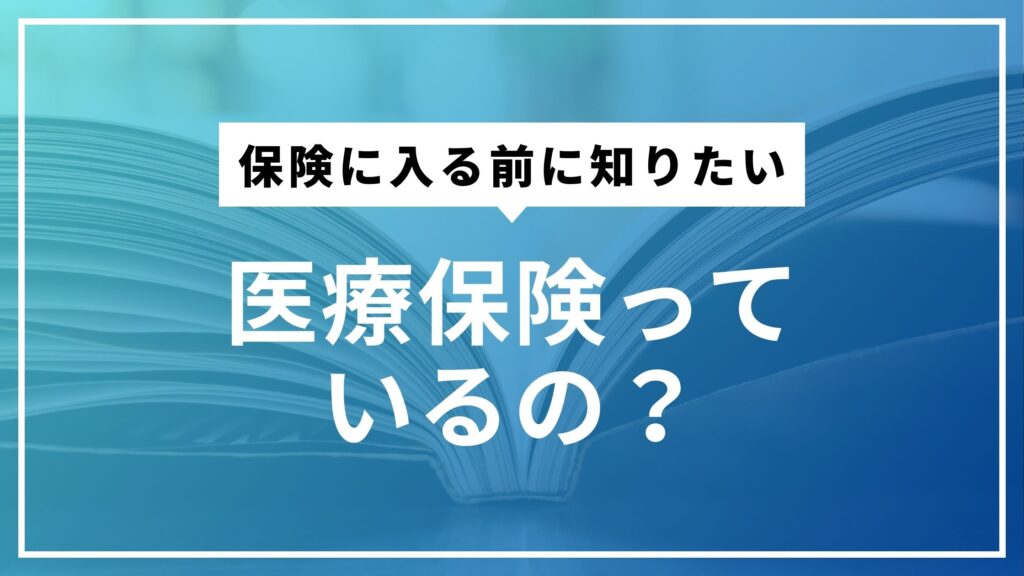突然ですが質問です。
控除額=手残り額と勘違いしていませんか?
控除はあくまでも控除なので、その金額がそのままもらえるわけではありません。
例えば生命保険の控除を使う場合、今の制度であれば年間で最大12万円の控除をすることができます。
仮に年収500万円の方がいたとして、この人にかかる所得税率は20%です。
生命保険料控除で得られるメリットは
12万円の控除額 × 20%の税率 = 2.4万円
これくらいが手取りに換算される金額です。
12万円の控除だから12万円手取りが増えると間違って認識している人は注意してください。
控除をマックスで使いたいから保険の見直しをしているって人がいますが、控除のために入る保険は本末転倒です。
必要な保険に入ったついでに控除があるというのが本来の形です。
控除=手取りではありません。
この記事では
- 控除の意味がわからない
- 生命保険料控除の枠ってなに?
- 手取額と控除額の計算方法
などの疑問を解決していきます。
控除とは?
生命保険料控除を理解するために、まずは控除の意味を知る必要があります。
たとえば、年収1,000万円の方の場合を考えてみます。(計算がかんたんなので)
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 | |
| 1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) | |
〈No.1410 給与所得控除〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
国税庁の所得計算に基づくと、年収1,000万円の方は1,950,000円を控除していいと書いてあります。
仮にこの所得控除がなければ、年収1,000万円の方にかけられる税率は33%なので、
1,000万円 × 33% = 330万円が所得税ということになります。
1,000万円稼いで330万円が徴収されるとしたら、まあ高いですね。
そこで給与所得控除を踏まえて計算し直すと、
(1,000万円 - 195万円) × 33% = 265万円となります。
課税される金額から控除額を差し引いて、所得税を抑えられました。
金額にして65万円の節減になっているので、大きいといえば大きいんですかね。
この例からわかる通り、控除とは課税されるおおもとの金額を低くするものです。
生命保険料控除は、給与所得控除+αくらいに考えておくと分かりやすいと思います。
控除があるとはいえ、税金って高いですね。。
生命保険料控除とは?
控除の前提を理解したら、次は生命保険料控除について考えていきます。
生命保険料控除には旧制度と新制度があるのですが、今回は新制度の方で解説をすすめます。
生命保険料控除の限度額は12万円となっていて、内訳は次の通りです。
一般生命保険料控除(最高4万円)
介護医療保険料控除(最高4万円)
個人年金保険料控除(最高4万円)
それぞれで4万円ずつ控除があり、全部で12万円という構図です。
■一般生命保険料控除の例
死亡保険、変額個人年金保険など
■介護医療保険料控除の例
医療保険、がん保険など
■個人年金保険料控除の例
定額個人年金保険
たとえば高額な医療保険とがん保険に入りまくったとしても、限度額の4万円までしか控除されないということになります。
生命保険料控除の金額
次は、いくらの保険料を払えば控除の枠を使いきれるのかを解説していきます。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
〈No.1140 生命保険料控除〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
年払い保険料が8万円以上だと、限度額の4万円を控除していいと書いてあります。
なので控除の枠を最低保険料で使い切ろうとすると、
8万円 × 3枠 = 24万円
年間24万円の保険料を支払えば、控除の枠をすべて使いきれることになります。
手取りに換算するといくらになるか
年間24万円の保険料を支払い、控除をすべて使い切ったとして計算してみます。
同様に年収1,000万円の場合で計算します。
生命保険料控除を使わず、給与所得控除のみを考慮した場合の手取り額は265万円でした。
(1,000万円 - 195万円) × 33% = 265万円
生命保険料控除(限度額12万円)を踏まえると、
(1,000万円 - 195万円 - 12万円) × 33% = 262万円になりました。
手取りが3万円増えました。
年間24万円を支払って、3万円手取りが増えることにどういう意味付けをするかは人それぞれです。
ただしひとつお伝えしておきたいのは、控除のために入る保険はムダということです。
【注意】よくあるセールストーク
「〇〇さん、個人年金保険料控除の枠がまだ4万円残っていますよ。このまま使わないのはもったいないですよね?」
このようなセールストークを、保険営業担当者からよく耳にしたことはないでしょうか。
一見すると損をしているように聞こえるこの言葉ですが、実際にはそうではないことを、ここまで見てくださったかたならわかるはずです。
まず、日本の税制についてです。
日本は累進課税制度を採用しており、収入が高くなるほど適用される税率が段階的に上がっていく仕組みになっています。
具体的には、年収195万円以下なら5%、195万円超330万円以下なら10%、330万円超695万円以下なら20%といった具合に税率が変動していきます。
この制度を理解した上で、実際の節税効果を計算してみましょう。
例えば、年収500万円の方が4万円の個人年金保険料控除を利用した場合、適用税率20%として計算すると、4万円×20% = 8,000円の節税効果となります。
たったの8,000円です。
一方で、個人年金保険の月々の保険料は通常1万円前後。
年間では12万円程度の支払いが必要です。
12万円支払って8,000円の節税メリット、という計算になります。
この差額を見れば、「節税のために加入する」という論理が破綻していることは明らかです。
さらに重要な注意点として、個人年金保険には様々なデメリットが潜んでいます。
途中解約すると元本割れするリスクが高く、運用実績が期待を下回る可能性もあります。
また長期契約となるため資金が固定化されてしまうという問題もあります。
賢明な選択のために、まずセールストークに惑わされず、必ず具体的な数字で節税効果を確認することが大切です。
同時に、保険料支払総額と節税効果を比較し、その資金を他の投資や貯蓄に回した場合のメリットも検討すべきでしょう。
そして何より、保険は「保障」が必要な場合に加入を検討する商品であり、節税は副次的なメリットでしかないということを理解する必要があります。
「もったいない」という言葉を使って感情に訴えかけ、冷静な判断を鈍らせようとする営業手法には要注意です。
このような営業担当者は、顧客の利益よりも自身の成約実績を優先する「Taker(奪う人)」であることを見抜く必要があります。
金融リテラシーを高め、自身の経済状況に本当に必要な金融商品を見極める目を養うことが、将来の資産形成には不可欠です。
安易な営業トークに流されず、冷静な判断を心がけましょう。
さらに、信頼できるファイナンシャルプランナーに相談したり、独自に金融教育を受けたりすることで、より賢明な判断ができるようになるはずです。
最後に覚えておきたいのは、「急かされる契約は要注意」ということです。
「今しかない」「この機会を逃すと損」といった言葉で焦りを煽られても、必ず一度立ち止まって考える時間を取りましょう。
顧客のことを考える通常の営業であれば、じっくりと検討する時間を与えてくれるはずです。