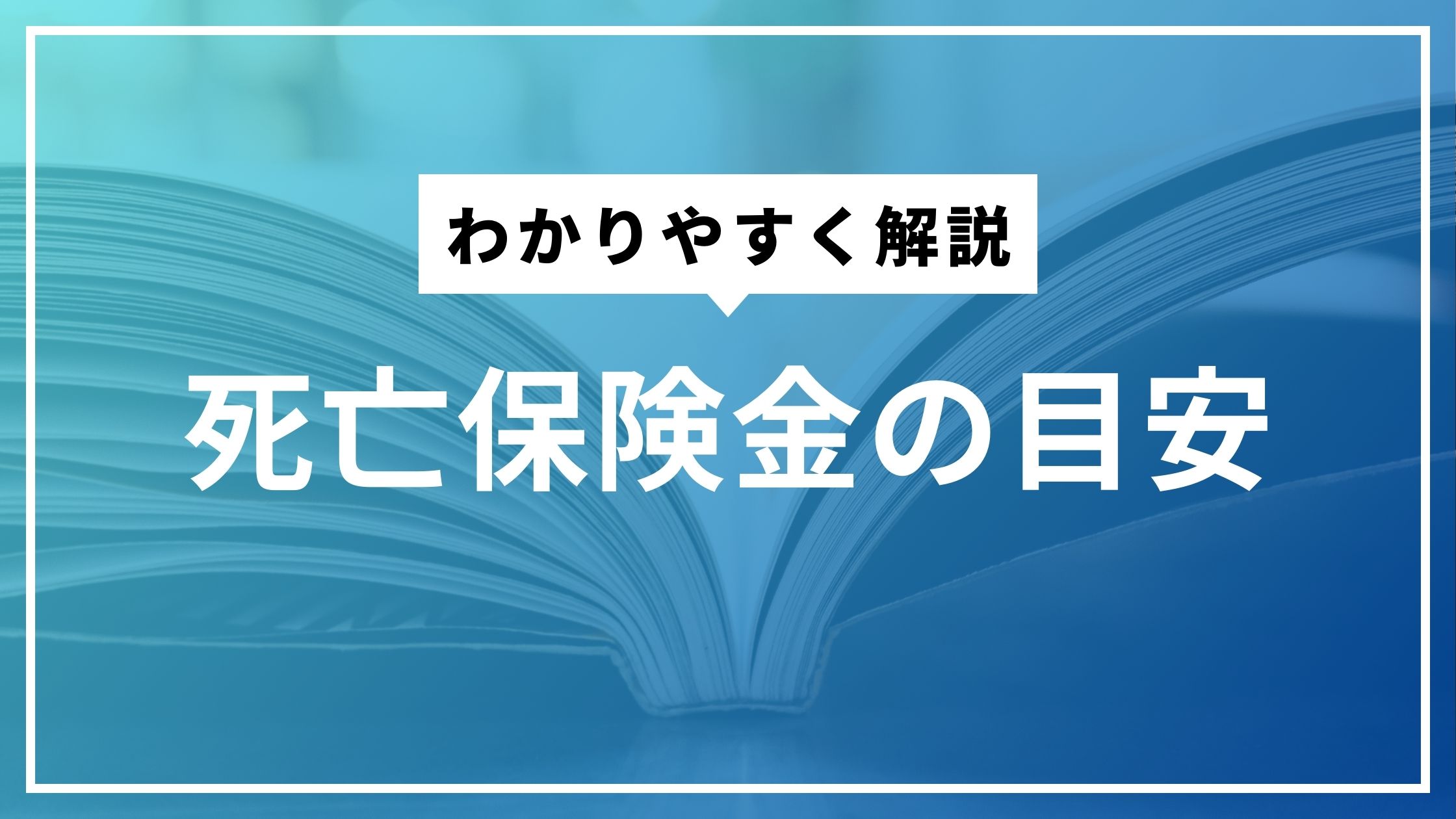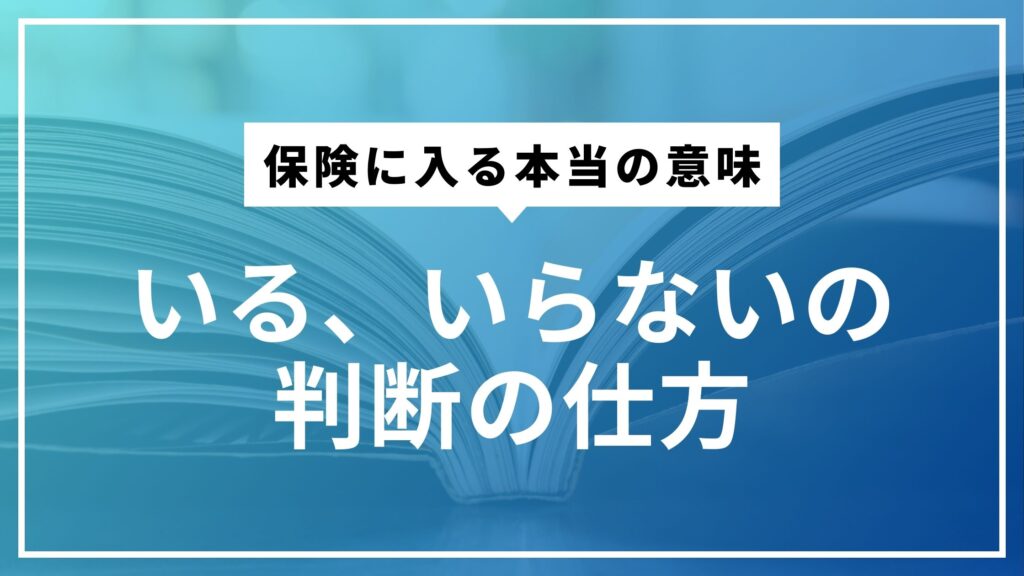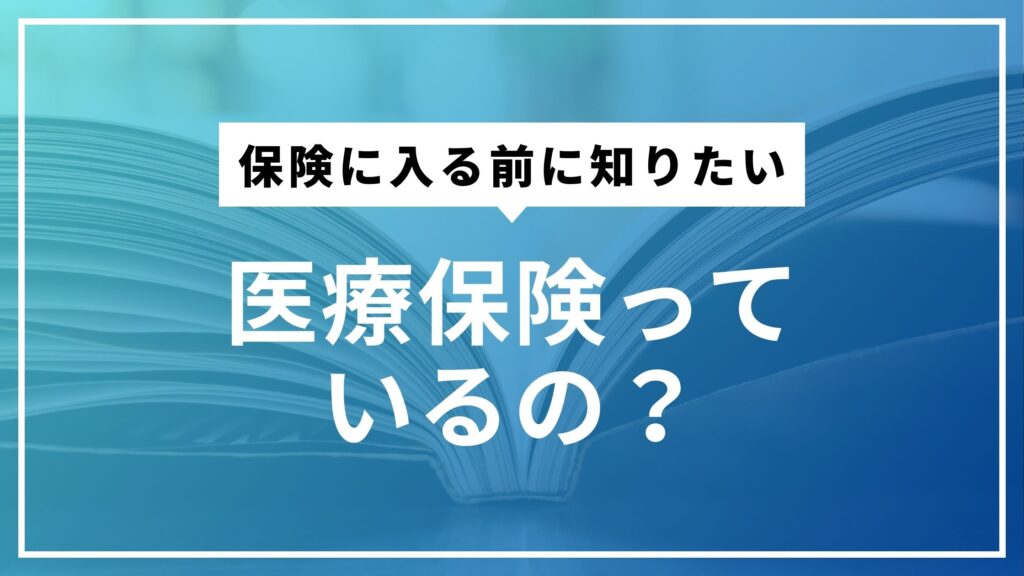生命保険を検討する際にまずはじめに出てくる疑問は、「生命保険の目安ってどれくらい?」ではないでしょうか?
一般的には年収の5倍とか、3,000万円くらいと目安はあるようです。
でもそう聞いて、「なるほど!じゃあ3,000万円の保険をかければいいですね!」
ってなる人はなかなか少数派だと思います。
この記事では
- 死亡保険金の目安の考え方がわからない
- そもそも死亡時にかかる費用はどのくらいか
ということを解決していきます。
目次
死亡保険金の目安
タイトルの通り、そんなもんない。
というのが僕の答えです。
たとえば、年収500万円の夫と専業主婦という条件で考えたとしても、子どもが一人なのか二人なのかで既に死亡保険金の目安は数千万単位で違います。
極端な話、夫婦で話し合った結果子どもの教育費のために死亡保険をかける必要はないとなれば、これもまた全然違う話になっていきます。
つまり、死亡保険金の目安なんて言葉自体がおかしいのです。
目安はこれくらいですって一般化してわかりやすくする効果はあると思いますが、真面目に考えている人ほど死亡保険の目安なんて言葉は使わないのではないでしょうか。
と言い切って回答しないのも何なので、一応平均額をお答えします。
生命保険文化センターの調査によると、死亡保険金の平均的な加入額は、男性が1,373万円、女性が647万円程度となっています。
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1220.html
<生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/2022(令和4)年度>
この金額は世帯年収や家族構成、住んでいる地域などを一切考慮していませんし、もちろんどんな価値観を持っているかなんていうのも反映されていません。
それでも平均額をひとつの参考にしたい方は、これくらいを目安にすればいいと思います。
死亡時にかかる費用
こどもの教育費とか残された遺族の生活費などの継続的に必要な費用はさておき、死亡時にかかる葬儀代・お墓代に焦点を当てます。
葬儀代
葬儀代の結論からお伝えします。
そんなもんないです。
いやまたかよって思われるかもしれませんが、実際そうです。
まず参列者がどのくらいかで、葬儀場の規模って違いますよね?
もうそれだけで、十把一絡げに平均いくらって言う考え方に無理があります。
それにどんな葬儀をするのかでも費用は全く違います。
葬儀の種類とは?
- 一般葬
- 家族葬
- 一日葬
- 直送
それぞれでかかる費用感は違います。
直送とは簡単に言うと、火葬のみを行う葬儀ですが、安く済ませようと思えば10万円前後くらいでできるようです。
「じゃあ自分が亡くなったときはそれでいいじゃん」
ってなるのは少し短絡的かもしれません。
自分はそれでいいかもしれませんが、残されたご遺族のことを考えてみてください。
それでいいはずないんです。
もしかしたら、冷たい家族だと周囲から批判的な目で見られる可能性だってあります。
そもそも、なぜ葬儀をする必要があるのでしょうか?
みんなやっているからでしょうか。
それが当たり前だからでしょうか。
葬儀をする生き物なんてのは人間だけで、他の動物はしません。
正解があるわけではありませんが、葬儀をするのは弔いたいという本能的欲求があるからではないでしょうか。
弔いたいという欲求があるにも関わらず、直送でただ安く済ませればOKなんてなるはずありません。
以上、僕の価値観から考えた葬儀代の費用は、少なくとも100万円は準備していたほうがいいかなと思います。
参考に家族葬をした場合の費用感を記載しておきます。
■家族葬(参列者20名程度)
総額:100~150万円
内訳:
基本セット料金(小規模な祭壇、棺など):50~70万円
式場使用料:20~30万円
人件費:10~15万円
料理接待費:15~20万円
返礼品:10~15万円
お布施:3~5万円
お墓代
お墓の費用は、墓石を建てることだけを想像しがちですが、実際には他にもいくつか費用がかかります。
- 永代使用料
- 年間管理費
などの継続的な支出はさておき、今回は死亡時にかかる費用として墓石代のみを考慮します。
最もシンプルな和型の場合:80~150万円
デザイン墓石:150~300万円
程度の費用がかかります。
なので結論は、葬儀代とお墓代あわせて200万円は準備しておいたほうがいいということになります。
必要保障額の考え方
収入 - 支出 = 必要保障額
言ってしまえばこれだけなのですが、具体的にしていくと、どうしてもややこしくなってしまいます。
【収入】
- パートナーの収入
- その他の収入(家賃収入などがあれば)
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金(世帯主が会社員・公務員の場合のみ)
【支出】
- こどもの教育費
- 住宅資金
- 生活費
仮に見込まれる収入と支出がどちらも5,000万円となれば、生命保険いらなくない?となるかもしれません。
こどもが生まれるタイミングで生命保険を検討する方が多いので、なにがあってもこどもの教育費はのこしたいと考えているのだと思います。
なのでせめて教育費の部分だけでも、いくら必要なのかということは知って置くべきです。
小・中・高までは公立なのか。
大学は私立の可能性があるか、国立か。
理系なのか文系なのか。
たとえば、4年間にかかる費用は国立に行った場合は約240万円で、私立理系の場合は約550万円と倍以上違います。
どういった進路を歩ませたいか考える必要があります。
でも極端な話、大学は奨学金で全部自分で払って行ってくれと考えるのであれば、保険として形にのこす必要はないのかもしれません。
死亡保険に入るメリット
死亡保険に入る大きな目的は、突然の収入喪失への備えです。
死亡保険金でのこされた遺族が困らないようにするために入っている方がほとんどだと思います。
ではそれ以外にメリットはあるか整理していきます。
メリット1:住宅ローン対策
これをメリットと言っていいか微妙ですが、住宅ローン対策として生命保険は優秀です。
団体信用生命保険、通称団信は住宅ローンを一括返済してくれる生命保険です。
たとえば4,000万円の住宅ローンを抱えている場合、死亡保険がないと残された家族がローンを継続して返済するか、家を手放すかの選択を迫られます。
団信に加入していれば、ローンを一括返済することができ、住み慣れた家に住み続けることができます。
住宅ローンを組む際は、団信への加入が義務付けられていることが多いので、入るのが当たり前になっている感じではあります。
メリット2:相続税対策
死亡保険金は、法定相続人1人につき500万円までが非課税という制度があります。
たとえば、配偶者と子ども2人の場合、1,500万円まで非課税となります。
ただしそもそも相続税が非課税の世帯であれば、特にメリットにはなりません。
メリット3:資金の準備がスムーズにできる
死亡時にはまず、葬儀費用としてまとまった資金が必要になります。
現実、自分が息を引き取る直前に「これを私の葬儀代に使ってくれ」と現金手渡しをする方なんてほとんどいません。
生命保険があれば数百万円の資金をかんたんに準備できるメリットがあります。
生命保険に入っていなければ、亡くなった方の口座からお金を引き出したり、親族の方が建て替えたりして対応します。
故人の預貯金は、死亡時点で相続財産となり、原則として口座は凍結されます。
つまり、家族といえども勝手に引き出すことはできません。
それに死亡時の預貯金引き出しにはルールがあり、
- 引き出し限度額が設定されている(150万円程度)
- 相続人であることを証明する書類の提出が必要(戸籍謄本など)
- 葬儀社への直接振込
など、めんどうな条件がついて回ります。
生命保険に入ることで、煩雑な引き出し条件を回避して、親族の手出しをなくせる効果が期待できます。
メリット4:ラストラブレター
ある保険会社では保険証券のことを「ラストラブレター」と言います。
どういう意味かと言うと、保険料を支払い続けることは、家族への思いやりを形にする一つの方法だと考えているということです。
自分が亡くなったあと、どんな生活をしてどんなお金の使い方をしてほしいかを形にするにはもってこいというわけです。
そのときに改めてご主人の思いやりを知るなんて感動的ですね。
ラストラブレターにストーリー性をもたせて保険を販売するセールストークもあるようですが、僕はあまり好きではありません。
あくまでも必要性重視です。
死亡保険の必要性が低い場合
- 十分な資産がある場合
- 配偶者にも十分な収入がある場合
- 子どもが独立している場合
- 大きな債務がない場合
こういう方は死亡保険の必要性は低いかもしれません。
もし年収10億円の妻がいたら、僕は絶対に生命保険に入りません。
なぜなら必要性がないからです。
まとめ
死亡保険金の目安や葬儀代、お墓代などについてお伝えしました。
まとめると、目安とか平均とかで一般化できるものではないという結論になります。
必要保障額は、真剣に考えれば考えるほど難しくなっていきます。
こどもの教育費と言っても進路によってはかかる費用が全然違います。
生活費だって細かく見ると光熱費やレジャー費、食費などに細分化されていきます。
詳しくは触れませんでしたが、年金はもっと難解です。
家族構成、年収、はたらき方によってもらえる年金額は異なります。
保険金をいくらに設定するかを、大まかにでも決めておくことをお勧めします。
死亡保険に入るメリットはいくつかありますが、資金の準備がスムーズにできるのは意外とそのときになったら助かるはずです。
相続のことを視野にいれて生命保険を検討してみてはいかがでしょうか。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!