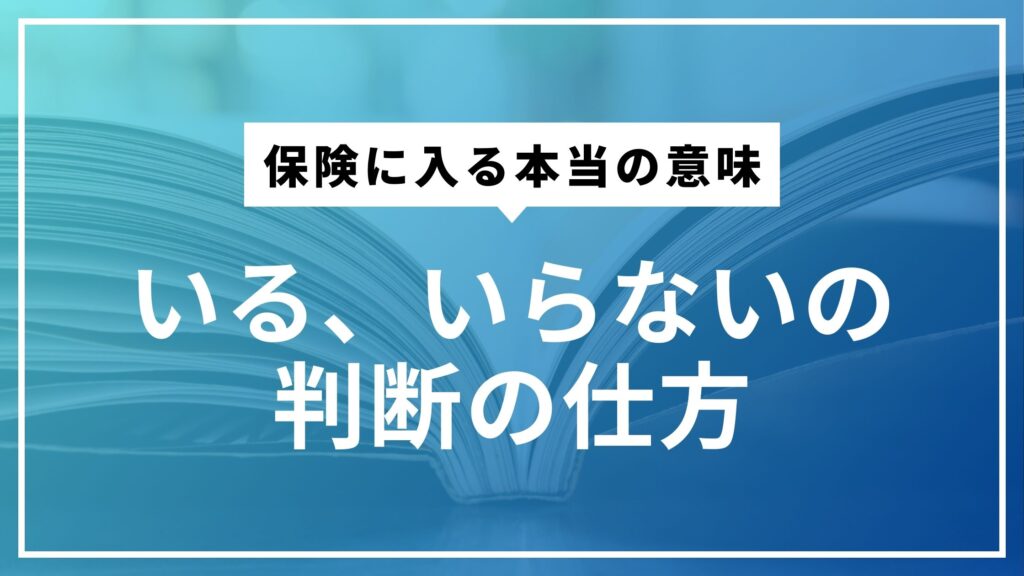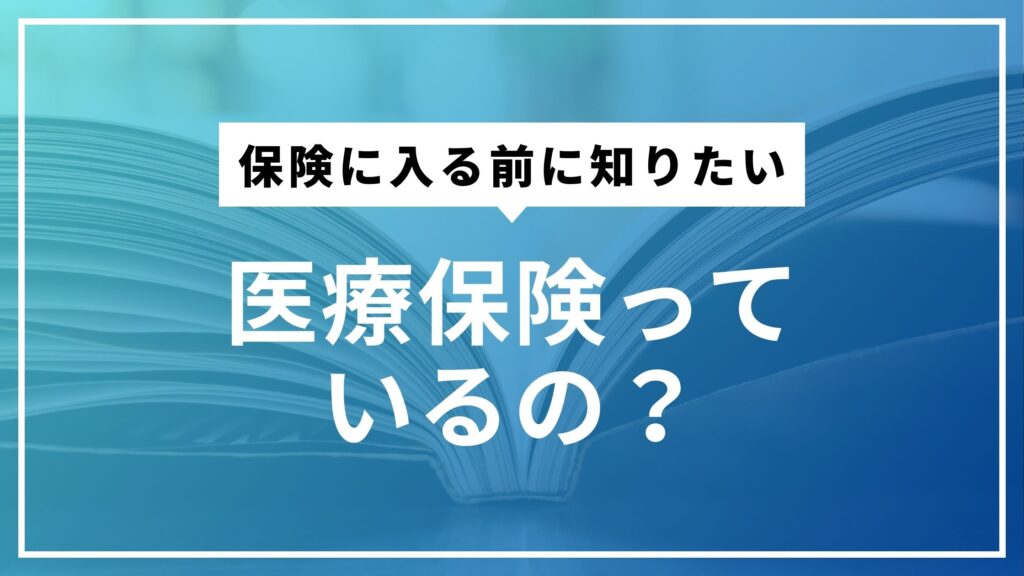- がん保険の加入率はどのくらい?
- がんのリスクは?
- 治療費の平均と最大はいくらくらい?
- 保険営業に言いくるめられたくない!
がん保険を勧められたときに、このようなことが気になったことがあるという方に向けて記事を書きます。
保険営業は保険を売ることが仕事と思っている人が多いので、いたづらに高額な保険を勧めてくるケースがあります。
必要な情報を伝えもせずに、不安を煽って販売してくる営業には気をつけましょう。
目次
がんは二人に一人の誤解
「がんは二人に一人がかかる病気です!保険に入らないなんて危ないです!」
という営業はもはや常套句。
たしかに間違ったことは言っていませんが、正しい情報を伝えてもいません。
というのも、二人に一人ががんになるというのは、生まれてから死ぬまでの一生涯を通しての確率なんです。
つまり、若い人と高齢の人を全部まとめた数字というわけです。
そもそも、数字の切り取り方で見せ方はおおきく変わることをお見せします。
次の表は1年の間にどれくらいの確率で「あなたはがんです」と診断されるかを表したものです。
1年間でがんと診断される確率
| 年代 | がんになる確率 |
|---|---|
| 20代 | 約3,700人に1人 |
| 30代 | 約1,150人に1人 |
| 40代 | 約360人に1人 |
| 50代 | 約160人に1人 |
| 60代 | 約84人に1人 |
| 70代 | 約50人に1人 |
| 80代 | 約35人に1人 |
出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」より
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
がんのリスクが最高潮になる80代でも35人に1人の確率となっています。
ここを切り取ると、全然二人に一人ではありません。
こんなデータは営業トークには使えないので、保険営業では次のようにして数字を見せていきます。
生まれてから84歳までにがんになるリスク
| 年代 | がんになる確率 |
|---|---|
| 男性 | 約62.4%(約1.6人に1人) |
| 女性 | 約47.4%(約2.1人に1人) |
これでだいたい二人に一人の割合になりました。
どのデータを信じればいいの?
なにも信じなくていい。
極論ですが、これが僕の答えです。
「おれは病気にはならん!」
なんていう人をたくさん見てきました。
最初は、「何を根拠にそんなこと言ってるんだろう」と思っていましたが、病気にならない可能性を否定できないことにも気づきました。
どれだけ莫大で精密なデータが出されたところで、その人に当てはまるかどうかは別問題。
人は自分が信じたいものしか信じないので、自分は死なないとか病気にならないとかって信じてる人は、それはそれで幸せなことです。
なぜ二人に一人の計算になるのか
「80代で35人に1人」なのに、なぜ生涯では「2人に1人」になるのか。
そんな疑問が浮かんできます。
これは、私たちが毎年くじを引いているようなものだと考えるとわかりやすいです。
たとえば、こんな例を考えてみます。
あなたは毎年1回、35枚のくじの中から1枚を引くとします。
1回だけなら当たる確率は35分の1と低いですよね。
でも、これを毎年続けるとどうでしょうか?
当たる確率はどんどん高くなっていきます。
具体的に計算すると
- 1年目:35人に1人
- 2年目:また35人に1人
- 3年目:さらに35人に1人…と毎年当たりを引く可能性があります。
かんたんにいうと、宝くじを1回買うのと、毎週買い続けるのとでは当選確率が大きく変わるのと同じ原理です。
「恐怖の宝くじ」
と言えば、がん保険のセールストークになるかもしれません(笑)
実際にかかる治療費は?
たとえば、大腸がんで3ヶ月の治療を受けた場合の費用を見てみます。
国立がん研究センターの調査によると、総医療費は約150-180万円くらいかかるようです。
- まず健康保険が適用され、70歳未満の場合は3割負担になります
- 180万円の3割 = 54万円
- そこから高額療養費制度が適用されます 【標準的な所得の場合(年収370万~770万円程度)】
- 1ヶ月目:上限額 約8万円
- 2ヶ月目:上限額 約8万円
- 3ヶ月目以降:上限額 約4万4千円(多数回該当の適用)
つまり、3ヶ月の治療したとして、実質的な自己負担は
8万円 + 8万円 + 4.4万円 = 約20.4万円
となります。
ただし、下記には注意。
- 入院時の食事代(1食460円)は別途必要
- 差額ベッド代を選択した場合は全額自己負担
- 世帯の所得区分によって上限額は変わる
「1000万円以上」というケースは、どんな場合に発生するのか
営業マンの中には
「この人はがんの治療に1,000万円以上かかってるんですよぉ。」
「もしこうなったら払えますかぁ?払えないですよねぇ!」
「怖くないですかぁ?怖いですよねぇ!」
と営業してくる人がいるかもしれません。
では具体的に先進医療を選択した場合の例を出します。
- 免疫療法:1回50-100万円×複数回
- 陽子線治療:総額250-300万円
- 高額な分子標的薬:1か月50-100万円×長期投与
これらの治療は「先進医療」に該当する場合が多く、健康保険が適用されないため、全額自己負担となることがあります。
たしかに、3割負担や高額療養費制度がつかえず、費用はかなり高額です。
おおくの方は実費でこの費用をまかなうのはむずかしいので、先進医療を専門で治療を行う病院では、
「先進医療特約がついた保険を契約していますか?」
とまず質問して、治療の可否を判断することもあるようです。
しかし、実際に先進医療を選択する患者さんは限られていて、がん患者の約1%といわれています。
1%がどのくらいの確率なのか、よりわかりやすくしてみます。
まず年間でがんと診断される確率は、40代で360人に1人程度です。
その中で先進医療を選択する確率が1%ということなので、これをかけ合わせると
1/360 × 1/100 = 1/36,000
と計算されます。
つまり40代の方が1年間で「がんになって、かつ先進医療を選択する」確率は約36,000人に1人ということになります。
これを身近な確率と比較すると
- 交通事故で重傷を負う確率:約1,000人に1人
- 宝くじ(ロト6)で5等に当たる確率:約1,000人に1人
- 落雷に打たれる確率:約10万人に1人
つまり、40代の方が1年間で「がんになって先進医療を選択する」確率は
交通事故で重傷を負う確率の約1/36。
落雷に打たれる確率の約3倍。
というレベルの確率だと言えます。
営業マンが言うような「1000万円以上」のケースはあくまでも最悪を想定しています。
- 先進医療を選択
- 長期の治療が必要
- 高額な薬剤を継続使用
という条件が重なった場合の極端な例と言えます。
ほとんどの方は、3割負担や高額療養費などの制度を利用することで、自己負担は大きく抑えることができます。
一般的に想定される医療費
先進医療はほとんどの方にはあてはまらず、高額療養費を使って治療をする可能性が高いとお伝えしました。
しかし高額療養費制度を使ったとしても、治療が長期的になればなるほどお金はかかります。
高額療養費制度(標準的な所得の場合)で
- 毎月の上限額:約8万円
- 4ヶ月目以降:約4.4万円(多数回該当)
この費用がかかったとして、治療期間が1-2年と長期になる可能性は否定できません。
逆算すると、総額では100万円前後の自己負担になることは往々にしてあります。
がん保険で注意するポイント
個人と法人で注意すべきポイントは変わります。
がん保険を法人で契約する場合
まず経営者の方が意外と盲点になっているのは、がん保険の給付金を正々堂々受け取って大丈夫か?ということです。
経営者の健康状態や事業の継続性を考えて、銀行から貸付を拒まれる可能性は少なからずあります。
なので保険金の受取口座をどうするのかまで考えるべきです。
- 事業保障のためにがん保険に入って保険金を受け取る。
- がんになったことが銀行に露呈する。
- 貸付を拒まれて事業が危うくなる。
なんてことになったら本末転倒ですからね。
借入の付き合いがない銀行の口座を指定することは、ひとつの対策としてありだと思います。
あとは税務の面でも注意が必要です。
仮にがん保険で100万円をもらったとします。
法人契約の場合、100万円は法人の口座に送金されるので、雑収入で処理されて法人税の課税対象になります。
全額福利厚生費で処理できれば個人/法人とも非課税になるのですが、現実それは厳しいです。
法人で100万円のがん保険を受け取って、それを全額非課税で個人に移転できると思っている社長は注意してください。
いざ保険金を受け取ったときに、「そんなの聞いてねーぞ!」とならないためにも、税金がかかると知っておいて損はないです。
ただ損金で処理できるメリットは大きいので、どういう目的で保険に入るかを担当の方に相談するのをオススメします。
がん保険を個人で契約する場合
めちゃくちゃ平たく言うと、がん保険は2つのタイプがあります。
- 入院日額で計算するタイプ
- 一時金で定額をもらうタイプ
それぞれ解説します。
どちらのタイプがおすすめか
仮に入院日額が5,000円という契約でがん保険に入ったとします。
30日間入院したとすると、
5,000円 × 30日 = 15万円
このように考えるのが入院日額で計算するタイプです。
一方、一時金で定額をもらうタイプは、お医者さんに「あなたにがんが見つかりました。」と診断された瞬間に保険金がもらえることが確定します。
通称がん診断給付金といって、100万円ていどの保障をつけるケースが多いです。
かんたんに言うと、がんと診断されたら100万円もらえる保険になります。
次に、保険金がいつどのタイミングでもらえるかに着目します。
入院日額を計算するタイプは、入院後にお金がもらえるようになります。
何日入院したかわからないと計算ができないからですね。
もう一方の一時金のタイプは、がんと診断されたら保険金が確定するので、入院前からお金をもらうことができます。
ここに大きな違いがあります。
個人のキャッシュフローを考えると、どう考えても入院する前から保険金がもらえた方がいいです。
なので結論、僕のオススメは一時金で定額をもらうタイプということになります。
注意すべきポイント
まず気をつけたいのが、上皮内がんの取り扱いです。
上皮内がんというのは、わかりやすくいうと「切除して治すがん」です。(厳密にいえば違いますが。)
保険商品によっては、「その程度のがんなんてがんと認められないので、保険金はお支払いできません。」なんてことがあります。
でもこっちからしたら、「いやいや、がんはがんでしょ」って思うじゃないですか。
なので、上皮内がんでもがん保険の対象となっているかはポイントとして抑えていた方がいいですね。
あとはがんは二人に一人についての考え方も整理したいポイントです。
二人に一人の見せ方は、ここまで読んでくださった方は理解していると思います。
見せ方はどうであれ、嘘は言っていないと受け入れたとしても、二分の一の確率でがんにならない未来も予測されます。
がんにならなかった場合でも、払い込んだ保険料は返ってきたほうがいいと考える方は、返戻があるがん保険を検討してもいいと思います。