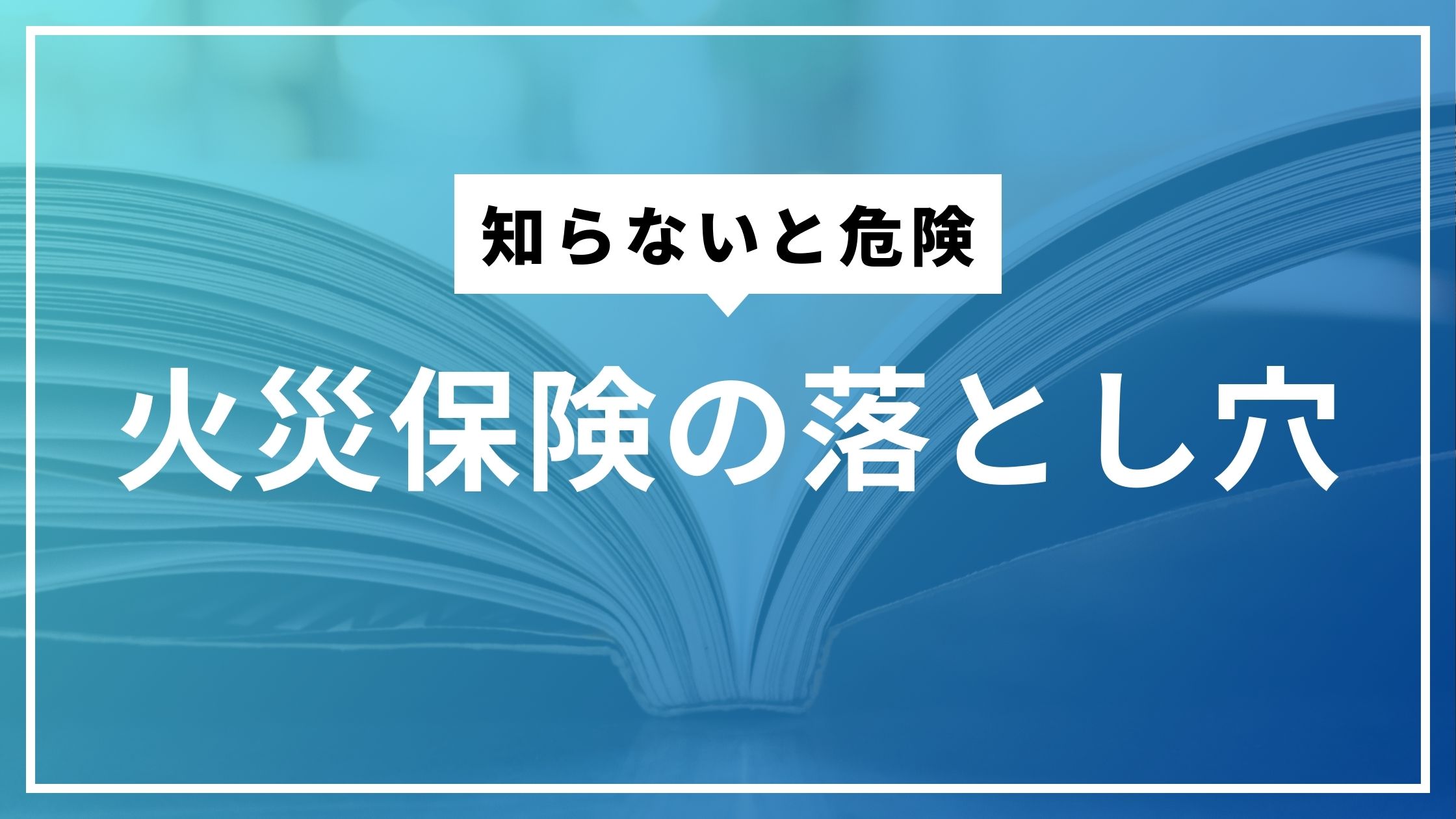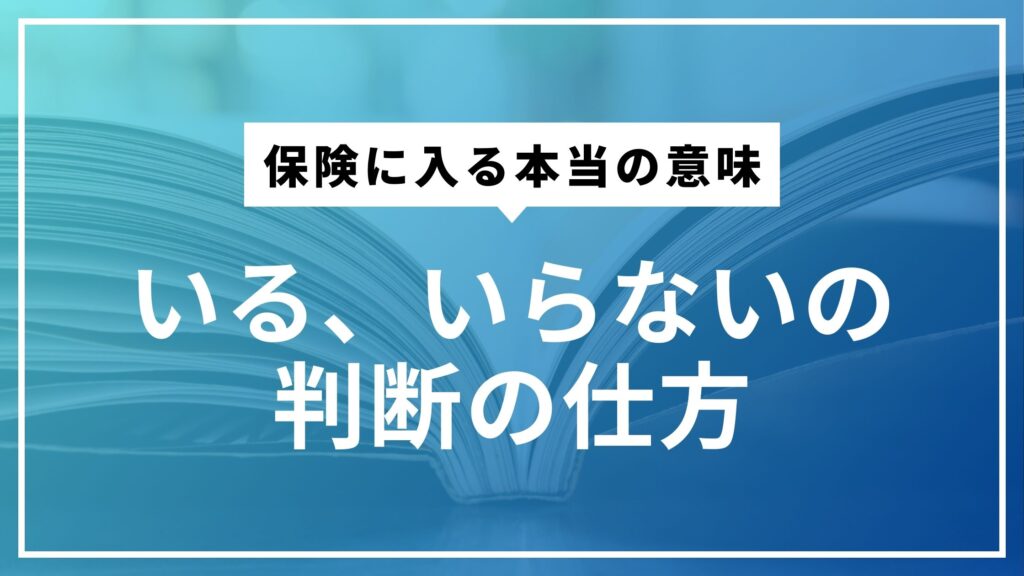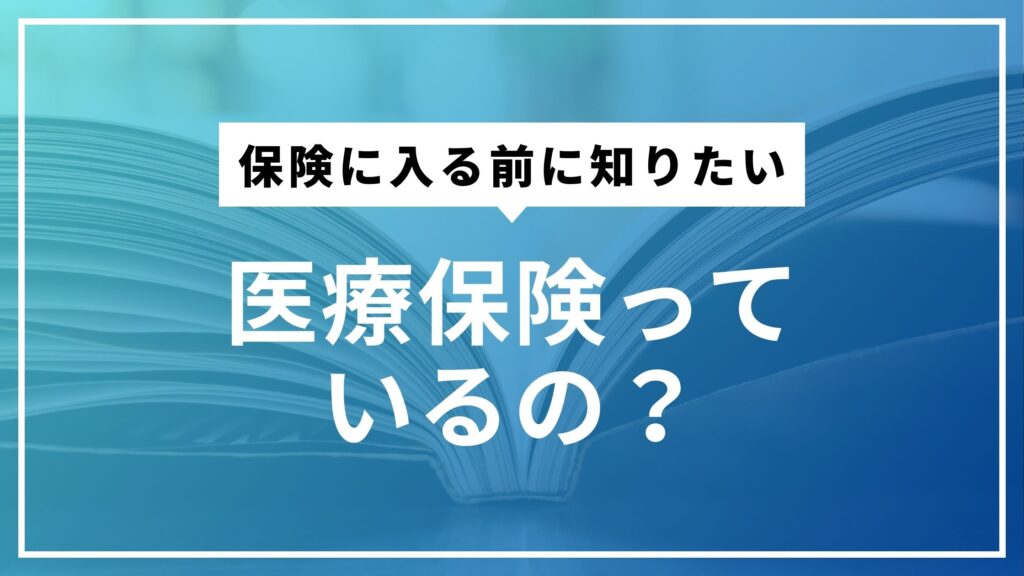こんなことでお悩みではありませんか?
- 「火災保険料が毎年上がって、家計が苦しい…」
- 「築20年以上経つ家だから、保険金額を下げてもいいのかな?」
- 「近所で火事があって怖かったけど、うちの保険金額で十分なのかしら…」
- 「火災保険の更新案内が届いたけど、内容が難しくて分からない…」
こんな不安や心配を抱えている方は、実はとても多いのです。
「火災保険は大切だけど、保険料の負担も気になる…」 このジレンマ、よく分かります。
でも、ちょっと待ってください。 保険金額を安易に下げてしまうと、実は大変なことになるかもしれないのです。
なぜ今、この記事を読む必要があるのか
最近、火災保険料が大幅に値上がりしています。その理由は
- 自然災害の増加による保険金支払いの増加
- 建築資材の価格高騰
- 人件費の上昇
このため、多くの方が保険料を抑えようと、保険金額を下げることを考えています。
でも、それは本当に賢い選択なのでしょうか?
要注意!多くの人が陥る「3つの誤解」
誤解その1:建物の価値は年々下がるから、保険金額も下げるべき
「築年数が経つにつれて建物の価値は下がっているから、保険金額も下げて保険料を安くしよう」
確かに、不動産としての建物の価値は年々減少します。
でも、火災保険で大切なのは「再建築費用」なのです。
再建築費用について次で解説します。
誤解その2:火災保険は「今の建物の価値」に対する保険
火災保険金額を建物の価値で決めるのは、実は違います。
火災保険で重要なのは「今、同じ建物を建てるといくらかかるか」という視点です。
物価上昇や建築費の高騰により、建築費用は年々上がっているのです。
誤解その3:保険金額を低く抑えても、満額もらえたら問題ない
これが最も危険な誤解です。
実は、保険金額を低く設定すると、火災での部分損害でも十分な保険金が受け取れない可能性があるのです。
知らないと危険!比例てん補とは?
「え?本当に、この保険金額で大丈夫なの?」
ある日、Yさん(45歳)は保険代理店でこんな言葉を投げかけられました。
築20年の自宅の火災保険を見直しに来たときのことです。
「だって、家だって古くなってるし、保険金額は下げても大丈夫だと思うんですけど…」
Yさんの考えは、多くの方が持っている”常識”でした。
でも、その”常識”が、実は大きな落とし穴になっているかもしれないのです。
火災保険の意外な真実
火災保険料の値上がりが話題になっています。
自然災害の増加や建築費の高騰が原因で、多くの方が保険料の負担に頭を悩ませているのです。
そんな中、よく聞く声があります。
「家は古くなってるんだから、保険金額を下げて保険料を安くしよう」
一見、とても理にかなった考え方に思えます。
でも、ここに火災保険の大きな落とし穴が隠されているのです。
築古物件の保険金額とその実態
ある日、私の住む街で火事がありました。
幸い人的被害はありませんでしたが、築25年の一軒家が大きな被害を受けました。
そして、家主のTさんが直面した現実は、想像以上に厳しいものでした。
25年前に2,500万円で建てた家。
経年劣化を考えて、保険金額を1,500万円に設定していました。
「これくらいあれば十分」と考えていたのです。
ところが…
「同じような家を建てようとすると、今は3,500万円かかります」
物価の上昇、建築資材の高騰、人件費の上昇。
様々な要因が重なって、建築費用は25年前の1.4倍になっていたのです。
9割が知らない火災保険の落とし穴
さらに衝撃的だったのは、「比例てん補」という仕組みの存在でした。
「火災保険は、建物が全焼した時だけのものではありません」
部分的な火災被害でも、保険金額が適正額より低いと、受け取れる保険金が大きく目減りしてしまいます。
例えば、実際の再建築費用が3,000万円の建物で、1,000万円の損害が発生したケース。
保険金額を2,000万円に抑えていると…
「実際の損害額が1,000万円でも、受け取れる保険金は666万円になってしまいます」
なぜこんなことが起こるのか?
それは「比例てん補」という仕組みのためです。
保険金額が実際の再建築費用に対して不足している場合、その割合に応じて保険金が減額されるのです。
これが「比例てん補」の正体です。
簡単に言うと、適正な保険金額に設定していないと支払われるお金が減額しますよということです。
賢い保険の見直し方、教えます
では、どうすれば良いのでしょうか?
火災保険は『今の建物の価値』ではなく、『今、同じ家を建てるといくらかかるか』を考えることが大切なんです。
例えば、スマートフォンが壊れた時、5年前の価格で新しいスマートフォンが買えるでしょうか?
同じように、家も今の価格で考える必要があります。
まず、現在の再建築費用を正確に把握すること。
というとハードルが高いので、保険会社で見積もりをとることをお勧めします。
保険会社では建築年や土地の広さで、「今、同等の家を建てるといくらかかるか」を計算してくれます。
どこの保険会社で見積りをとっても、この金額に大差はありません。
見積もりをとるだけなので、簡単に再建築費用を把握することができます。
そして、将来の費用上昇も考慮に入れること。
物価は常に変動していますから、定期的な見直しも大切です。
保険料の負担が気になる場合は、保険金額を下げる前に、まず複数の保険会社の見積もりを比較してみましょう。
同じ補償内容でも、保険会社によって保険料が大きく異なることがあります。
また、建物と家財のセット割引を利用したり、長期契約で保険料を抑えたりする方法もあります。
保険料を抑える5つの方法
保険金額を下げずに保険料を抑える方法があります。
1.複数の保険会社から見積りを取る
- 保険会社によって保険料は最大で30%程度違うことも
- オンラインで簡単に比較可能
コツは「条件を揃えること」
A社では保険金額を5,000万円、B社では4,000万円なんて見積りのとり方をしていると、とうぜん比較検討の材料にはなり得ません。
2.建物と家財の保険をセットにする
- セット割引が適用される場合が多い
- 総合的な保障も手に入る
家財にも保険をかけている方は、建物とセットで契約した方が安くなります。
建物と家財を別々の保険会社で契約している方がいますが、保険料と管理のしやすさ的にはまとめてしまう方がオススメです。
3.長期契約を検討する
- 長期契約の方が保険料が安い
- 契約期間中の保険料上昇を回避
1年で契約するよりも、5年で契約した方が安いです。
基本的には、契約期間が長くなればなるほど保険料が安くなると思って大丈夫です。
昔は住宅ローンに合わせて30年の火災保険契約とかができたんですが、今は5年間が最長の保険期間になっています。
火災保険料はどちらかというと年々増加する傾向にあります。
例えば5年契約にすると、その5年間は契約時の保険料になるので、保険料の上昇を回避できる可能性が高いです。
4.免責金額を設定する
- 小額の損害は自己負担
- その分保険料が安くなる
免責とは、簡単に言うと自己負担のことです。
例えば免責を10万円に設定していたとします。
台風で窓ガラスが割れて30万円の修理代が必要になりました。
免責を10万円に設定しているので、30万円のうち10万円は自己負担しなければなりません。
保険会社からもらえる保険金額は20万円となります。
という感じです。
このような仕組みになっているので、免責金額を高く設定すればするほど保険料は安くなります。
5.補償内容を最適化する
- 不要な特約を見直す
- 本当に必要な補償を見極める
結局ここがいちばん大事で難しいとこです。
住んでいる地域、建物の構造などはそれぞれ違うので一概に判断することはできませんが、ひとつだけ具体例をご紹介します。
例えば「水災」という保障があります。
水災は保険料に占める割合が比較的高いので、見直す価値が大きいといえます。
ハザードマップを見て、自宅が水害リスクの高い地域に所在しているかを把握できたらいいですね。
マンションの2回以上に住んでいる方なんかは、水災の保障を外していいんじゃないかなと思います。
上層階の部屋に水が侵入してくるのは、なかなかにレアケースではないでしょうか。
まとめ:大切な家族の住まいを守るために
昔はかなり長期で契約できましたが、いまの火災保険契約期間は最長で5年になっています。
定期的な見直しの機会を設けずとも、強制的に5年後には見直ししなければなりません。
もちろん更新のタイミングで保険料が安くなる可能性もありますが、高くなる可能性の方が高そうですね。。
適切な保険金額を設定することで
- 災害時の経済的な不安を解消
- 家族の生活を確実に守れる
- 将来の安心を手に入れられる
保険料の負担は確かに大きいかもしれません。
でも、比例てん補の仕組みや補償内容を理解することで、本当の意味での「安心」を手に入れることができます。
ぜひ、この記事を読んだことをきっかけに、ご自身の火災保険を見直してみてください。
専門家への相談や、複数の保険会社からの見積り取得から始めてみましょう。