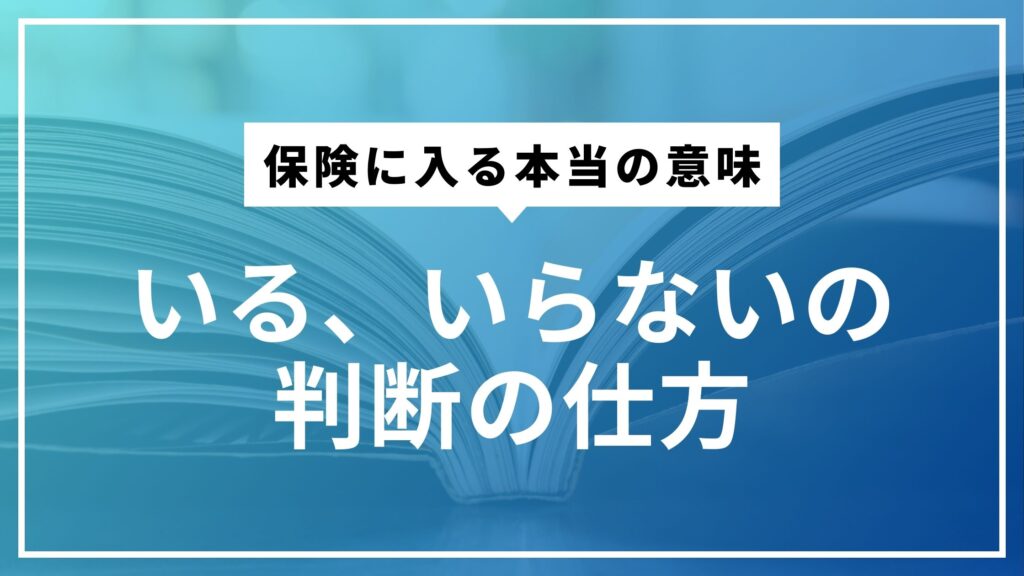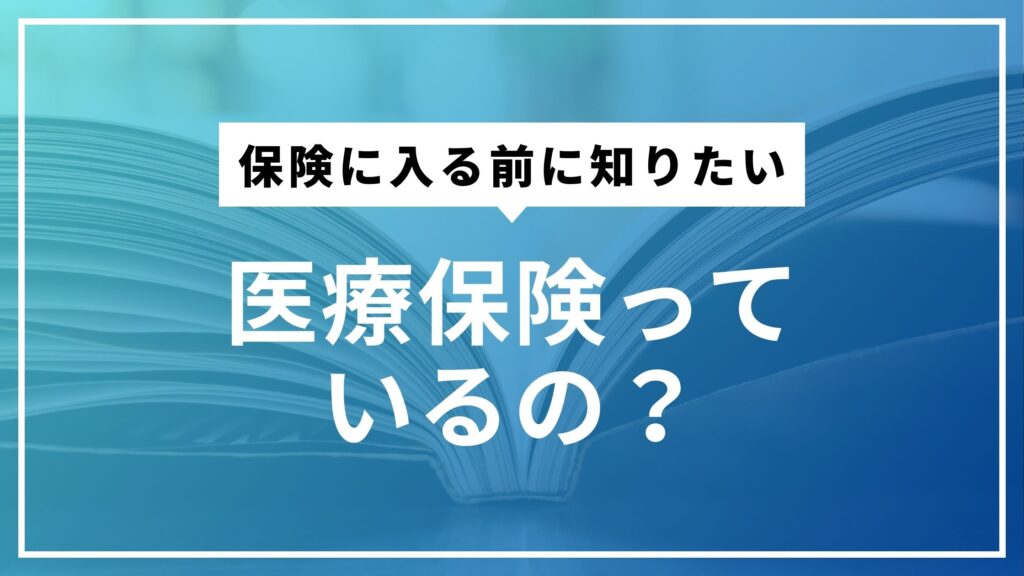「法人保険は節税になるの?」
「どんなメリットがあるの?」
といった疑問を持つ経営者は多いですよね。
法人保険は単なる税金対策ではなく、会社の存続を左右する経営ツールとしての側面を持っています。
実は、中小企業経営者の約68%が「自分に何かあった場合の会社の存続」について不安を感じていることが報告されています。
この記事では、単なる「保険の説明」ではなく、「経営者の悩みを解決するための法人保険の正しい活用法」をお伝えします。
目次
法人保険の基本と会社経営での3つの役割
法人保険とは何か – シンプルに理解する
法人保険とは、法人が契約者となって加入する保険を指します。
そういう意味では、法人で加入する
- がん保険
- 医療保険
- 死亡保険
なども、法人保険となります。
この記事では、「死亡保険」について深堀りしていきます。
特に難しく考える必要はありません。
契約者が法人というだけで、保険の基本的な役割は個人とほぼ同じです。
お金を払うのは会社。
経営者や従業員が被保険者。
万が一のときは会社が保険金を受け取る仕組みです。
経営者と会社を守る3つの主要な役割
① リスク対策ツール(事業保障)
中小企業経営実態調査(日本政策金融公庫 2022)によれば、経営者に万一があった場合、約6割の企業で業績が30%以上悪化することが示されています。
また経営者の多くは「借入金の即時返済要求」を懸念しています。
一般的に、中小企業では経営者である「あなた」への依存度が高いこと予想されます。
エースで4番で監督の経営者に、万が一があった際のリスクに備えるのが、法人保険の第一の役割です。
② 資金準備ツール(資金積立)
法人保険を退職金等の積み立てとして活用する方は少なくありません。
中小企業における役員退職金の平均支給額は約2,500万円です。
これくらい払い出すのは余裕という方もいれば、計画的な準備が必要な方もいます。
退職金の積立はべつに保険にこだわらなくてもできますが、事業保障と積立の機能をかね備えてるのは保険だけですね。
③ 事業承継ツール(事業承継対策)
中小企業の事業承継時には、相続税・贈与税などの税金負担が発生します。
債務超過(赤字)の企業であればかかりませんが。
東京商工リサーチの調査(2023)によれば、事業承継時に必要な資金の調達が困難だったと回答した企業は約63%に上ります。
でも事業承継とか相続って、はっきりいって眠たい話ですよね。
数カ月後とかの話ではないし、対策を考えたとしても売上は上がらない。
気持ちはわかります。
でも1年よりも、10年、15年スパンで考えたほうができることは多いですし、スムーズに承継を行えることは間違いありません。
筆者の考え方:保険にムダに加入しない
基本的には個人保険と考え方は同じです。
貯金がまともにできていない家庭に、無理をして貯蓄性がある保険はオススメはしません。
かけすてのやすい保険で十分です。
法人の場合は、経費で落とせるということもあり大雑把に考えがちですが、必要な分を必要なだけ入るのが合理的です。
経営者が知っておくべき法人保険6つの効果
① 財務体質の改善効果(貸借対照表の改善)
法人保険に加入すると、会社の資産の部に「保険積立金」という項目が計上されます。
解約返戻金相当額を資産計上することが基本となります。
カンタンにいうと、貯金をしているようなものです。
【例】年間300万円の保険料で10年間積み立てた場合
- 解約返戻金: 約3,200万円(平均予定利率1.5%として計算)
- 自己資本比率: 15%→35%に向上
- 借入金調達力: 調達可能額が約2倍に
保険を使えば、資金調達力が上がるのか!すごい!
とはなりませんよね。
年間300万円を貯金に回しているようなものですから、元々しっかり利益が出ている企業だとわかります。
保険を使わずとも、財務体質を強化することは可能です。
現金があるから保険に入って、そしてよくわかんないけど、結果的に財務が強化されているという会社もたくさんあります。
設備投資という名の、クルーザーや高級車にお金が消えていくよりかはマシですかね。
② 役員退職金の確保
経営者の退職金は一時に大きな金額が必要になり、会社の資金繰りを圧迫することがあります。
中小企業庁の調査によれば、約78%の中小企業が「退職金支給による資金繰りへの悪影響」を懸念しています。
【例】退職金3,000万円を保険で準備する場合
- 予定退職金:3,000万円
- 貯蓄型保険:年280万円×10年で3,100万円の満期金
- 経営への影響:毎年の利益から少しずつ準備するため負担感が軽減
貯蓄型保険で計画的に退職金を確保することができます。
ただし、国税庁の税務調査において、過大な役員退職金は指摘事項の上位に入っています。
過大と指摘された部分は、損金不算入となるのでご注意ください。
③ 事業継続資金の確保
中小企業の経営者が就業不能になった場合、平均で月間売上の約27.5%が減少するというデータがあります。
【例】経営者が急死した場合
- 売上減少:月間売上30%減(業界平均値)
- 固定費:人件費などは引き続きかかる
- 事業継続率: 保険がない場合40%、保険活用で95%
※生命保険文化センター「企業経営と生命保険に関する調査」(2022)を基にしたモデルケースより
経営は「ヒト」「モノ」「カネ」が必要だといわれます。
すべて欠かせない要素ですが、ヒトがいなければなにもできません。
給与支払いが滞れば、従業員が辞めるかもしれませんし、経営者の穴を埋めるような人材だっていなくなるかもしれません。
そうなれば、とうぜん会社は回らなくなります。
立て直しにかかる時間を考慮して、保険の保障額を決めるようにしましょう。
④ 事業承継・相続対策
事業承継における最大の障壁として、「相続税・贈与税の負担」が挙げられます。
法人保険を、死亡保険金や解約返戻金を納税資金に充てることができます。
【例】相続税が8,000万円かかる場合
- 納税原資①:現金/預貯金で2,000万円
- 納税原資②:死亡退職金で2,000万円
- 納税原資③:死亡保険金で4,000万円
納税資金を確保するイメージはこんな感じです。
実際には、退職金支給時の相続性の試算や、ご遺族に必要額が確実に支払われるように「退職金規定」の策定も重要となります。
⑤ 借入金の返済
経営者に万一のことがあった場合でも、銀行にきちんとお金を返せるかは重要です。
【例】借入金1億円の返済が残っている場合
- 個人保証が相続される
- 死亡保険は借入金の1.5倍を準備
個人保証とは、経営者が会社で借りたお金を返せなくなった場合、個人の預貯金・不動産などの資産をすべて投げ売ってでも返済すべきだという考え方です。
厄介なのが、この個人保証も財産と同じように相続されていくということです。
なにも分からないご遺族からしたら、「急に借金をかぶらされた」と考えてしまうわけです。
そうならないために保険に入ります。
注意点としては、仮に1億円のお金をのこすには、1億円の保険では足りない点です。
会社に死亡保険金が払い出された際に、約30%の法人税がかかるからです。
借入金 × 1.5倍の保険金額が目安となります。
⑥ 従業員の福利厚生
従業員の定着に、「福利厚生の充実」は重要な要素です。
なぜなら、「福利厚生制度の充実度」は従業員の定着率に影響する上位5要素に含まれているからです。
中小企業でも福利厚生の差が採用競争力に直結するといって差し支えありません。
【例】
- ハーフタックスプラン(死亡保険)
- 医療保険/がん保険
例えば、ハーフタックスプランで死亡保険に加入すると、保険料の半分を経費で落としつつ従業員の死亡リスクに備えることができます。
ハーフタックスプランは、条件を満たしたうえで養老保険に入ることで成立します。
詳しい説明をしだすと日が暮れるので、詳細は保険の担当者におたずねください。
ハーフタックスプランでは、満期の受取金を従業員の退職金に当てることもできます。
医療保険・がんほけんを福利厚生として考える場合は、従業員向けに手頃な保険料のものを選択するのが一般的です。
税金メリットはない
法人保険の税務処理の基本
かつては節税目的で加入されていた法人保険ですが、2019年の税制改正で実質的な節税効果はなくなりました。
節税保険ではなく、課税の繰り延べ保険という表現が正しいです。
現在の損金算入割合
- 最高解約返戻率50%以下: 全額損金算入可能
- 最高解約返戻率50%超70%以下: 保険料の70%を損金算入
- 最高解約返戻率70%超85%以下: 保険料の40%を損金算入
- 最高解約返戻率85%超: 保険料の20%を損金算入
出典:国税庁「法人税基本通達9-3-5の2」(2023)]
節税効果がない理由
法人が生命保険に加入しても、保険金や解約返戻金を受け取る際には益金計上が必要となるためです。
そのため、保険料を支払っている間だけの節税となり、課税の繰り延べになるのです。
例えば、年払い100万円で70%を損金算入できる保険に入っていたとします。
法人税が約30%とすると年間の節税額は、
70万円 × 30% = 21 万円
年間で21万円節税できるので、これを10年も続ければ210万円の節税です。
でも解約するときに、節税できていたこの210万円はきちんとお国に召し上げられます。
うまく調整されるようにできているわけです。
解約返戻金は雑収入として計上されます。
つまり、法人の利益になるということです。
利益に対しては法人税がかかるので、保険料を支払っている間に節税できていた金額が徴収されるしくみです。
この例でいうと、解約返戻金にかかる税金が210万円になるということですね。
ではすべての保険に節税効果がないかといわれると、そうではありません。
一応、節税ができる保険はあるので事項でご紹介します。
法人保険の30万円特例
法人保険の30万円特例とは、年間30万円までなら支払った保険料を全額損金にしていいというものです。
わかりやすく、30万円特例と呼ばれています。
- 最高解約返戻率が70%以下の死亡保険
- 第3分野の保険(医療保険・がん保険など)
たしかに節税効果はありますが、年間30万円です。
節税がしたい経営者からしたら満足できる金額ではないと思われます。
【筆者の考え】
節税を目的とする場合は、30万円特例の優先順位は低いです。
たいした効果は得られません。
必要な保険に入ったうえで、おまけで節税できているくらいの感覚でいいと思います。
法人保険で失敗しないための4つのチェックポイント
チェックポイント①: 会社のキャッシュフローを圧迫していないか
「なんか資金繰りが厳しい」
「保険を解約しよう」
こういう経営者は少なくないですが、それでは少し遅いかもしれません。
売上が増えているのに利益がのこらない。
利益を出しているのにお金が増えない。
このような違和感を覚えたら、保険といっしょに会社のキャッシュフローの見直しをオススメします。
会社の財務と照らし合わせて、会社が支払える保険料のアッパーを知ることも大事です。
チェックポイント②: 解約返戻率に関する誤解はないか
法人保険に関する相談・苦情が「解約返戻金に関する誤解」に起因していることがあります。
特に「〇年で元本回収」という説明に関するトラブルが多いと報告されています。
「毎年のキャッシュフロー表」や「解約返戻金の推移表」を説明してくれるパートナーをつけましょ。
会社を回しながらすべてをご自身で行うのは、少し無理があります。
そのために、税理士や保険の担当者がいます。
チェックポイント③: 税務メリットの誤解はないか
基本的には、法人保険に節税効果はありません。
また過大と指摘されると、損金算入ができなくなるケースもあります。
せっかく税金上で大きくメリットをとれる退職金でも、損金不算入となれば元も子もありません。
税金のことはやはり顧問税理士に相談するべきです。
税金上のメリットを重視するあまり、保険本来の保障機能が疎かになっているケースが多く見られます。
あくまでも、税金メリットは『結果』と考えるべきです。
チェックポイント④: 代理店の選定は適切か
保険のプロが、保険に関しての知識が不足しているケースは少ないかもしれません。
ですが、その先の税務や会社の財務諸表を読み解く知識が不足していることはよくあります。
最低でも、決算書の読める保険屋さんからアドバイスをもらうことをオススメします。
また、相続や事業承継など、さまざまな専門家を適宜紹介できるネットワークをもっているかも、いざというときに頼れるポイントです。
まとめ:経営戦略としての法人保険を最大限に活用するために
法人保険は、単なる「節税対策」ではなく、会社と経営者を守り、未来につなげるための「経営ツール」です。
特に中小企業経営者にとっては、限られた経営資源を有効活用し、予期せぬリスクから会社を守るための強力な味方になります。
この記事でお伝えした7つのメリットと選び方のポイントを参考に、あなたの会社の成長段階と経営課題に最も適した保険設計を行ってください。
そのためには、目先の節税効果だけでなく、「会社を守る」「資金を準備する」という視点からバランスよく法人保険を活用することが大切です。
保険のプロフェッショナルと良いパートナーシップを築き、長期的な視点で戦略を構築していきましょう。